良いワインは良い血を作るの読み方
よいわいんはよいちをつくる
良いワインは良い血を作るの意味
「良いワインは良い血を作る」は、質の良いワインを適量飲むことで、血液の質が向上し、健康が増進されるという意味です。
この表現は、単純にワインの飲酒を推奨しているのではなく、「質の良いものを適切に摂取することの大切さ」を教えています。古い時代の医学的知識に基づいているため、現代の栄養学とは異なる考え方ですが、本質的には「良質なものを選んで摂取することが健康につながる」という普遍的な教えを含んでいます。使用場面としては、食事や飲み物の質について語る際や、健康的な生活習慣について話すときに用いられます。現代では、ワインに含まれるポリフェノールなどの抗酸化物質が健康に良いという科学的知見もあり、この格言が完全に間違いというわけではありません。ただし、あくまで適量摂取が前提であることは言うまでもありません。
由来・語源
実は、「良いワインは良い血を作る」という表現は、日本の伝統的なことわざではありません。これは西洋の格言「Good wine makes good blood」の直訳として日本に入ってきた言葉なのです。
この格言の起源は古代ギリシャ・ローマ時代にまで遡ります。当時の医学では「四体液説」という考え方が主流で、人間の健康は血液、粘液、黄胆汁、黒胆汁の4つの体液のバランスによって決まるとされていました。この理論の中で、良質なワインは血液の質を向上させ、健康を促進すると信じられていたのです。
中世ヨーロッパでは、水の衛生状態が悪かったため、ワインは日常的な飲み物として重宝されました。特に修道院では、ワインは神聖な飲み物であると同時に、健康維持のための薬としても位置づけられていました。「良いワインは良い血を作る」という考えは、こうした時代背景の中で定着していったのです。
日本には明治時代以降、西洋文化の流入とともにこの格言が紹介されました。ただし、日本酒文化が根強い日本では、ことわざとしてよりも、ワインの効能を説明する際の表現として使われることが多かったようです。
豆知識
古代ローマでは、ワインに水を混ぜて飲むのが一般的でした。純粋なワインをそのまま飲むのは野蛮な行為とされ、教養ある人は必ず水で薄めていたのです。この習慣は衛生面だけでなく、「良いワインは良い血を作る」という考えにも影響を与えました。
中世の修道院では、修道士たちがワイン造りの技術を発展させ、「神の恵み」として品質向上に努めました。彼らは祈りを込めてワインを醸造し、それが健康な体と魂を作ると信じていたため、この格言の精神的な側面も強調されていました。
使用例
- 彼は高級ワインを少しずつ味わいながら、良いワインは良い血を作るという言葉を思い出していた。
- 安いワインばかり飲んでいたが、良いワインは良い血を作るというし、たまには奮発してみよう。
現代的解釈
現代社会では、「良いワインは良い血を作る」という格言は、健康志向の高まりとともに新しい解釈を得ています。科学的研究により、赤ワインに含まれるレスベラトロールやポリフェノールが心血管系の健康に良い影響を与えることが明らかになり、この古い格言が現代医学によって一部裏付けられる形となりました。
しかし、現代では飲酒に対する見方も大きく変化しています。アルコールの健康リスクについての認識が高まり、WHO(世界保健機関)は「安全な飲酒量は存在しない」という見解を示しています。このため、この格言を文字通り受け取ることには注意が必要です。
一方で、この格言は「質の良いものを選ぶ」という現代的な価値観と合致しています。オーガニック食品、無添加食材、フェアトレード商品など、品質や製造過程にこだわる消費者が増える中で、「良いものは体に良い」という考え方は広く受け入れられています。
また、SNS時代においては、高品質なワインを楽しむライフスタイルが「丁寧な暮らし」の象徴として注目されています。量より質を重視する現代人にとって、この格言は単なる飲酒の推奨ではなく、生活全般における品質への意識を表現する言葉として機能しているのです。
AIが聞いたら
赤ワインに含まれるレスベラトロールという成分が、血管の老化を防ぐ働きをすることが科学的に証明されています。この物質は、血管の内側を覆う細胞(血管内皮)を守り、血液の流れをスムーズにする効果があります。
フランス人は脂っこい料理をよく食べるのに心臓病が少ないという「フレンチパラドックス」の謎も、実は赤ワインの抗酸化作用で説明できます。ポリフェノールという成分が体内の「サビ」を防ぎ、血管の炎症を抑えているのです。
驚くべきことに、適量の赤ワイン(1日グラス1杯程度)を飲む人は、まったく飲まない人より心血管疾患のリスクが約20%低いという研究結果があります。これは、ワインのアルコール自体にも善玉コレステロールを増やす効果があるためです。
さらに興味深いのは、レスベラトロールが「長寿遺伝子」と呼ばれるサーチュイン遺伝子を活性化することです。つまり、細胞レベルで老化を遅らせる可能性があるのです。
ただし、これらの効果は「適量」が前提です。飲みすぎれば逆効果になります。古代の人々が経験的に感じ取った「良いワインは良い血を作る」という知恵が、現代の分子レベルの研究で裏付けられているのは本当に驚きです。
現代人に教えること
「良いワインは良い血を作る」という格言が現代人に教えてくれるのは、「質を重視する生き方」の大切さです。忙しい現代社会では、つい安さや手軽さを優先してしまいがちですが、本当に価値のあるものを選ぶ目を養うことの重要性を、この言葉は思い出させてくれます。
これはワインに限った話ではありません。食べ物、人間関係、仕事、趣味など、人生のあらゆる場面で「良いもの」を見極める力が求められています。良いものは時に高価だったり、手に入れるのに時間がかかったりしますが、それが私たちの心と体を豊かにしてくれるのです。
また、この格言は「適量」の大切さも教えています。どんなに良いものでも、過度に摂取すれば害になります。バランス感覚を持って、自分にとって本当に必要なものを見極める知恵が大切なのです。現代人にとって、この古い格言は「豊かさとは何か」を考えるきっかけを与えてくれる、貴重な言葉と言えるでしょう。

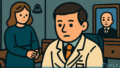

コメント