民は之に由らしむべし、之を知らしむべからずの読み方
たみはこれによらしむべし、これをしらしむべからず
民は之に由らしむべし、之を知らしむべからずの意味
このことわざの本来の正しい意味は、「民衆が自然に納得して従えるような道理に基づいた政治を行うべきで、無理に複雑な知識や理屈を押し付けるべきではない」ということです。
これは為政者に対する教えで、民衆を愚かに保つという意味ではなく、むしろ民衆の立場に立った思いやりのある政治を求めているのです。真に優れた政治とは、民衆が自然に「これは正しい」と感じられるような、分かりやすく道理にかなったものでなければならないという考えです。複雑な理論や難解な説明を必要とするような政策は、本当に良い政治とは言えないということですね。現代でも、リーダーシップや組織運営において、部下や民衆に無理な説得をするのではなく、自然に納得できるような環境や仕組みを作ることの大切さを教えています。
由来・語源
このことわざは、中国の古典『論語』の「泰伯第八」に記載されている孔子の言葉が由来です。原文は「民可使由之、不可使知之」で、これが日本に伝来し、江戸時代頃から広く知られるようになりました。
興味深いのは、この言葉が長い間、為政者が民衆を愚民化する思想として解釈されてきたことです。しかし、現代の論語研究では、句読点の位置によって全く異なる意味になることが明らかになっています。従来は「民は、之に由らしむべし。之を知らしむべからず」と読まれ、「民衆には政治に従わせればよく、その理由を教える必要はない」という意味とされていました。
ところが、古代中国の文章には句読点がなく、「民は之に由らしむべし、之を知らしむべからず」という読み方が正しいとする説が有力になっています。この場合、「民衆が自然に従えるような政治を行うべきで、無理に知識を押し付けてはいけない」という、まったく正反対の意味になるのです。孔子の他の教えを考えると、後者の解釈の方が孔子の思想により合致していると考えられています。
使用例
- 真のリーダーは民は之に由らしむべし、之を知らしむべからずの精神で、複雑な説明より自然に納得できる方針を示すものだ
- 政治家が難しい理屈ばかり並べるのを見ると、民は之に由らしむべし、之を知らしむべからずという言葉を思い出してしまう
現代的解釈
現代社会では、このことわざは二つの相反する文脈で語られることが多くなっています。一つは従来の誤った解釈に基づく「情報統制」や「愚民政策」の正当化として使われるケースです。特に政治の世界では、都合の悪い情報を隠す際の言い訳として引用されることがあります。
しかし、本来の正しい意味を理解すると、現代の情報化社会においてより重要な示唆を得ることができます。インターネットの普及により、私たちは膨大な情報にさらされていますが、情報が多ければ多いほど良いというわけではありません。むしろ、情報過多によって判断力が鈍ったり、本質を見失ったりすることも少なくありません。
企業経営においても、この教えは非常に有効です。優れた経営者は、従業員に対して複雑な経営理論を押し付けるのではなく、誰もが納得できるシンプルで明確なビジョンを示します。アップルのスティーブ・ジョブズが「シンプルであることは、複雑であることより難しい」と語ったように、本当に価値のあるものは自然に人々の心に響くものです。
教育の分野でも同様で、優れた教師は難解な理論を並べるのではなく、学習者が自然に理解できるような環境を作り出します。これこそが孔子の真意だったのかもしれませんね。
AIが聞いたら
この「誤読」事件は、句読点という小さな記号が持つ恐るべき政治的影響力を物語っている。問題の核心は「之を知らしむべからず」の解釈にある。従来は「民に真実を知らせてはならない」と読まれ、為政者が愚民政策を正当化する根拠として2000年以上使われてきた。
しかし1970年代、中国の学者たちが句読点の位置を変えて「之を知らしむべからず」を「知らしむべからず(知らせないのはいけない)」という否定の否定として読み直した。つまり「民には従わせるべきだが、理由を知らせないのは良くない」という民主的解釈が生まれたのだ。
驚くべきは、この解釈変更が単なる学術的議論に留まらなかったことだ。中国では改革開放政策の理論的支柱として活用され、「民に知らせるべき」という情報公開の根拠とされた。同じ漢字の羅列が、時には独裁を、時には民主化を支える道具となったのである。
この現象は言語の二重性を鮮明に示している。古典は客観的真理ではなく、読み手の時代背景や政治的必要性によって意味が創造される。孔子の本意がどちらだったかは重要ではない。重要なのは、同一のテキストが正反対の社会システムを正当化できるという、解釈の持つ無限の可能性と危険性なのだ。
現代人に教えること
このことわざが現代人に教えてくれる最も大切なことは、「本当の知恵とは、相手の立場に立って物事を伝える力」だということです。私たちは知識社会に生きているため、つい多くの情報や理論を相手に伝えることが良いことだと思いがちです。しかし、相手が自然に納得できないような説明は、結局のところ意味がありません。
家庭でも職場でも、人を動かそうとするとき、複雑な説明や理屈よりも、相手が「なるほど、それは確かにそうだ」と心から思えるような伝え方を心がけることが大切です。これは決して相手を軽く見ることではなく、むしろ相手への深い思いやりの表れなのです。
また、リーダーの立場にある人は、部下や仲間に対して自分の知識をひけらかすのではなく、みんなが自然に同じ方向を向けるような環境づくりに力を注ぐべきでしょう。真のリーダーシップとは、人々が自発的に行動したくなるような状況を作り出すことなのです。
この古い教えは、現代のコミュニケーションにおいて、相手の心に寄り添う大切さを教えてくれています。あなたも日々の会話で、この精神を活かしてみてはいかがでしょうか。

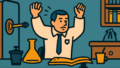
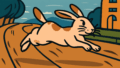
コメント