 ことわざ
ことわざ 血は争えないの意味・由来・使い方|日本のことわざ解説
血は争えないの読み方ちはあらそえない血は争えないの意味「血は争えない」とは、親子や血縁者の間には、意識しなくても自然と現れる共通点があり、それは血筋によるものなので避けることができないという意味です。この表現は、主に親子間で見られる身体的特...
 ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ 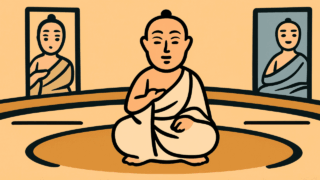 ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ 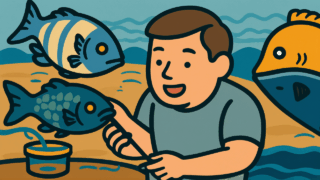 ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ 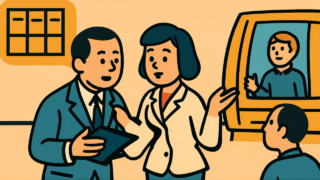 ことわざ
ことわざ