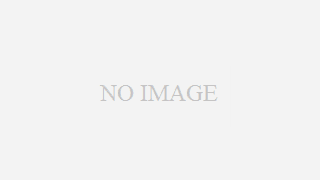 ことわざ
ことわざ 竿の先に鈴の意味・由来・使い方|日本のことわざ解説
竿の先に鈴の読み方さおのさきにすず竿の先に鈴の意味「竿の先に鈴」は、小さな工夫や準備が大きな成果を左右するという意味のことわざです。このことわざは、些細に見える配慮や準備こそが、物事の成否を決める重要な要素になるということを教えています。釣...
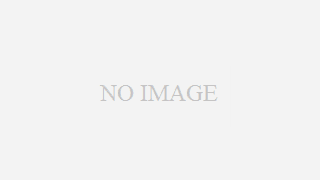 ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ 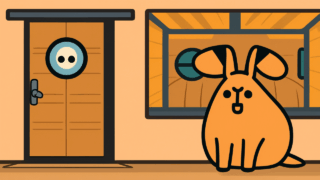 ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ