 ことわざ
ことわざ 魚は殿様に焼かせよ、餅は乞食に焼かせよの意味・由来・使い方|日本のことわざ解説
魚は殿様に焼かせよ、餅は乞食に焼かせよの読み方うおはとのさまにやかせよ、もちはこじきにやかせよ魚は殿様に焼かせよ、餅は乞食に焼かせよの意味このことわざは、物事にはそれぞれに適した方法や心構えがあることを教えています。魚は急いで焼くと表面だけ...
 ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ 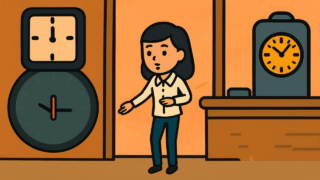 ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ 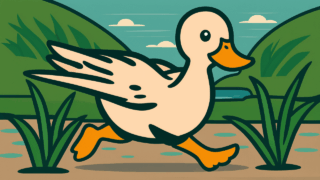 ことわざ
ことわざ 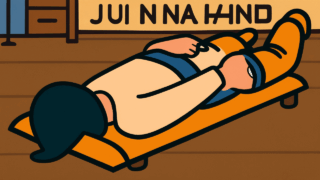 ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ