 ことわざ
ことわざ 酒は百毒の長の意味・由来・使い方|日本のことわざ解説
酒は百毒の長の読み方さけはひゃくどくのちょう酒は百毒の長の意味「酒は百毒の長」とは、酒があらゆる害悪や災いの根源となる最も危険なものであるという意味です。ここでの「百毒」は数多くの毒や害を表し、「長」は首領や頭領を指しています。つまり、酒は...
 ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ 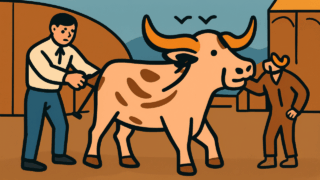 ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ 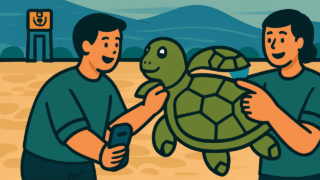 ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ