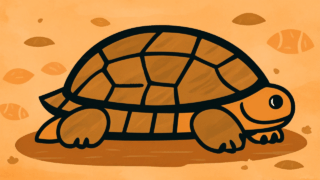 ことわざ
ことわざ 亀の甲より年の功の意味・由来・使い方|日本のことわざ解説
亀の甲より年の功の読み方かめのこうよりとしのこう亀の甲より年の功の意味このことわざは、どんなに貴重なものや立派に見えるものであっても、長年の経験によって培われた知恵や技能の方が実際には価値があるという意味です。年を重ねることで得られる経験や...
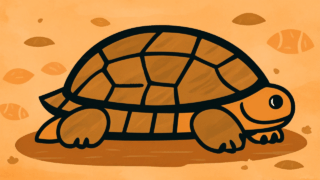 ことわざ
ことわざ 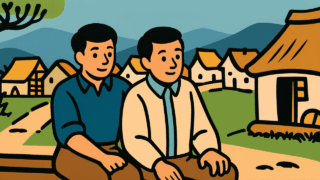 ことわざ
ことわざ 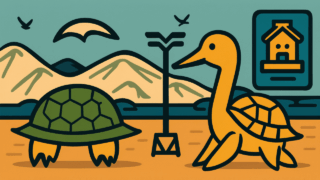 ことわざ
ことわざ 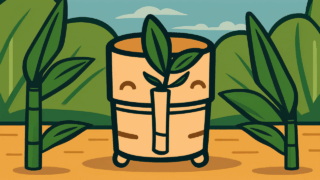 ことわざ
ことわざ 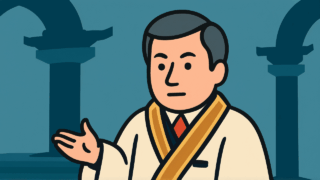 ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ