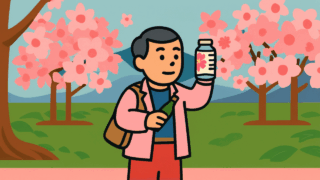 ことわざ
ことわざ 酒なくて何の己が桜かなの意味・由来・使い方|日本のことわざ解説
酒なくて何の己が桜かなの読み方さけなくてなんのおのがさくらかな酒なくて何の己が桜かなの意味このことわざは、「酒がなければ、自分にとって本当の桜の楽しみとは言えない」という意味です。つまり、何かを心から楽しむためには、それに付随する要素や雰囲...
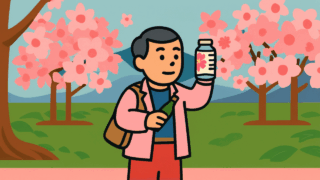 ことわざ
ことわざ 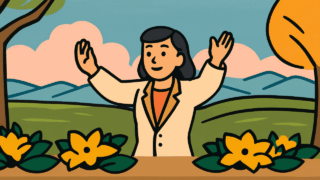 ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ 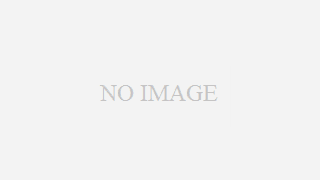 ことわざ
ことわざ 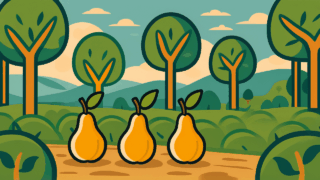 ことわざ
ことわざ 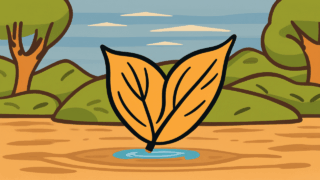 ことわざ
ことわざ 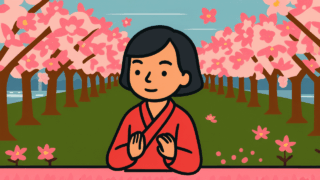 ことわざ
ことわざ 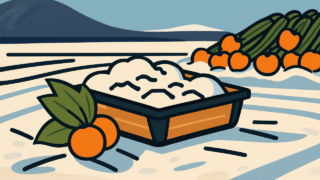 ことわざ
ことわざ