 ことわざ
ことわざ 早起きは三文の徳の意味・由来・使い方|日本のことわざ解説
早起きは三文の徳の読み方はやおきはさんもんのとく早起きは三文の徳の意味「早起きは三文の徳」は、早起きをすることで得られる利益や恩恵は、金額にすればわずか三文程度の小さなものだという意味です。このことわざは、早起きを推奨しているのではなく、む...
 ことわざ
ことわざ 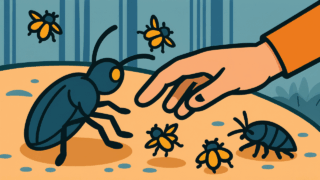 ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ