 ことわざ
ことわざ 怪力乱神を語らずの意味・由来・使い方|日本のことわざ解説
怪力乱神を語らずの読み方かいりょくらんしんをかたらず怪力乱神を語らずの意味「怪力乱神を語らず」とは、不思議な現象や超自然的な事柄、常識を超えた力業や社会を乱すような話題について語らないという意味です。これは単に迷信や神秘的なことを避けるとい...
 ことわざ
ことわざ 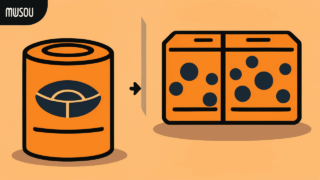 ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ 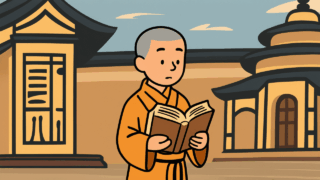 ことわざ
ことわざ