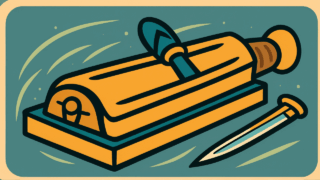 ことわざ
ことわざ 伝家の宝刀の意味・由来・使い方|日本のことわざ解説
伝家の宝刀の読み方でんかのほうとう伝家の宝刀の意味「伝家の宝刀」とは、いざという時のために普段は使わずに温存している、最も頼りになる手段や能力のことを指します。この表現は、本当に困った時や重要な局面でのみ使用する「最後の切り札」「奥の手」と...
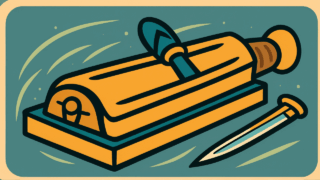 ことわざ
ことわざ 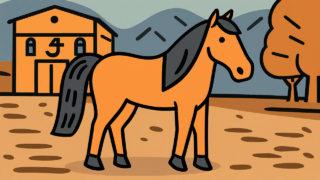 ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ 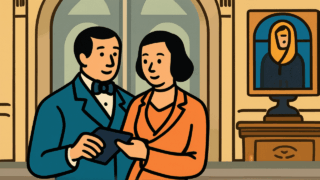 ことわざ
ことわざ 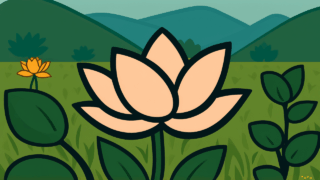 ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ