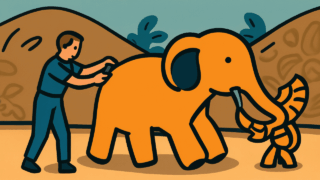 ことわざ
ことわざ 驥尾に付すの意味・由来・使い方|日本のことわざ解説
驥尾に付すの読み方きびにふす驥尾に付すの意味「驥尾に付す」とは、優れた人物に従って行動することで、自分も良い結果を得ることができるという意味です。名馬の尻尾につかまって進むように、実力のある人や成功している人のそばにいることで、自分一人では...
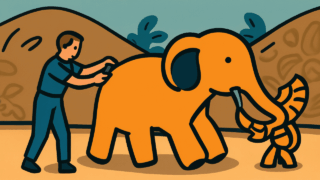 ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ 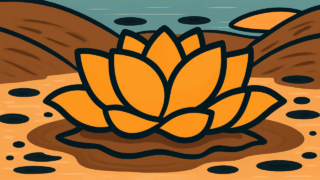 ことわざ
ことわざ 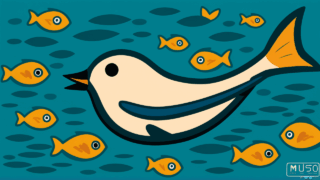 ことわざ
ことわざ 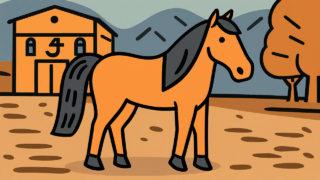 ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ 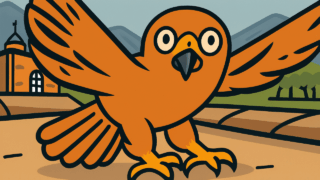 ことわざ
ことわざ 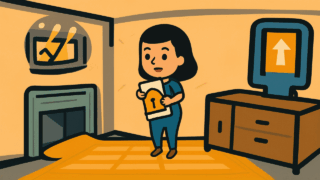 ことわざ
ことわざ