 ことわざ
ことわざ 智に働けば角が立つの意味・由来・使い方|日本のことわざ解説
智に働けば角が立つの読み方ちにはたらけばかどがたつ智に働けば角が立つの意味このことわざは、理性や知恵に従って正論を述べたり、筋道立てて物事を判断したりすると、周囲の人との間に摩擦や対立が生じてしまうという意味です。つまり、頭で考えて「正しい...
 ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ 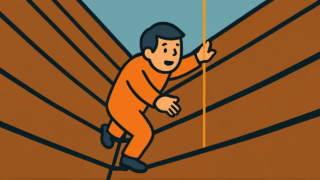 ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ