 ことわざ
ことわざ 提灯持ちの意味・由来・使い方|日本のことわざ解説
提灯持ちの読み方ちょうちんもち提灯持ちの意味「提灯持ち」とは、権力者や上司などに対してへりくだり、その人の機嫌を取ったり世話を焼いたりして付き従う人のことを指します。この表現は、主に批判的な文脈で使われることが多いですね。単純に誰かを手伝う...
 ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ 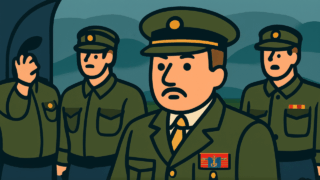 ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ 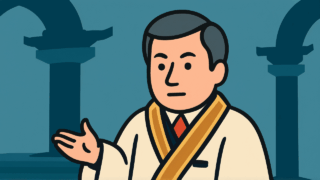 ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ 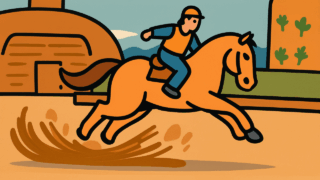 ことわざ
ことわざ 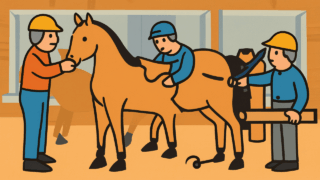 ことわざ
ことわざ