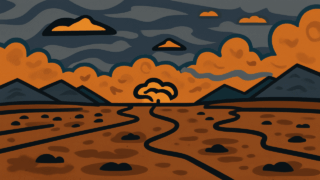 ことわざ
ことわざ 雲泥の差の意味・由来・使い方|日本のことわざ解説
雲泥の差の読み方うんでいのさ雲泥の差の意味「雲泥の差」とは、二つのものの間に非常に大きな違いがあることを表すことわざです。この表現は、能力や品質、価値などに圧倒的な開きがある状況で使われます。単に「違いがある」というレベルではなく、比較する...
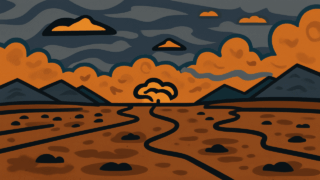 ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ 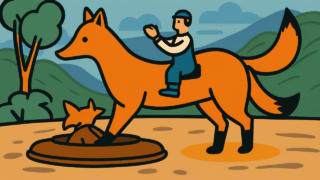 ことわざ
ことわざ 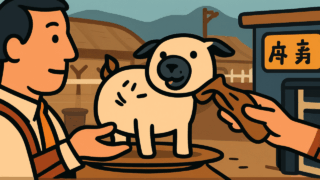 ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ 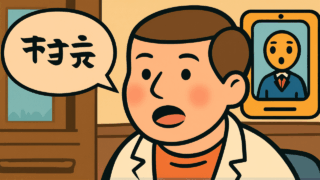 ことわざ
ことわざ