 ことわざ
ことわざ 三度目の正直の意味・由来・使い方|日本のことわざ解説
三度目の正直の読み方さんどめのしょうじき三度目の正直の意味「三度目の正直」とは、一度目、二度目と失敗や思うようにいかないことがあっても、三度目には必ず成功するという意味のことわざです。このことわざは、人間の学習と成長のプロセスを表現していま...
 ことわざ
ことわざ 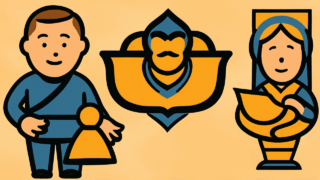 ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ 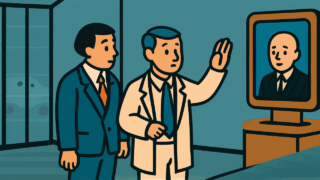 ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ 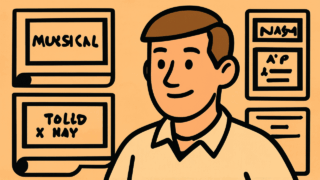 ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ