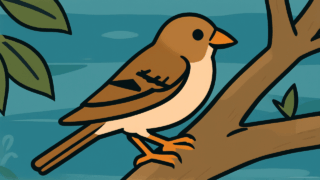 ことわざ
ことわざ 着た切り雀の意味・由来・使い方|日本のことわざ解説
着た切り雀の読み方きたきりすずめ着た切り雀の意味「着た切り雀」とは、着ている物以外に着替えがなく、非常に貧しい状態を表すことわざです。雀が一年中同じ羽毛で過ごしているように、一枚の着物しか持たず、それを着たきりで他に着替える物がない貧乏な様...
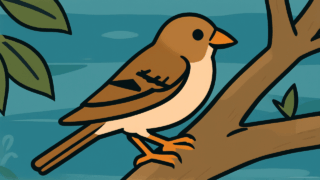 ことわざ
ことわざ 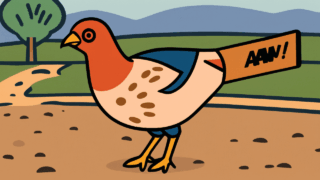 ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ 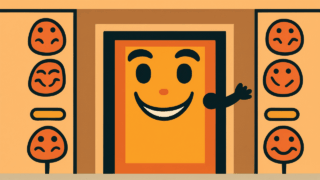 ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ 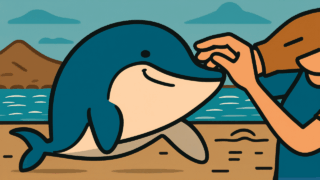 ことわざ
ことわざ 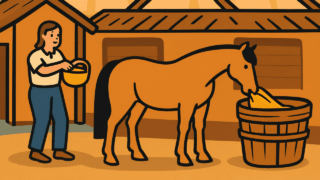 ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ 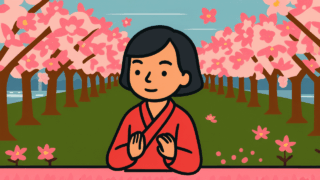 ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ