 ことわざ
ことわざ 借りてきた猫の意味・由来・使い方|日本のことわざ解説
借りてきた猫の読み方かりてきたねこ借りてきた猫の意味「借りてきた猫」とは、普段は活発で元気な人が、慣れない場所や初対面の人の前で、急におとなしく遠慮がちになってしまう様子を表すことわざです。このことわざは、環境の変化によって人の行動が大きく...
 ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ 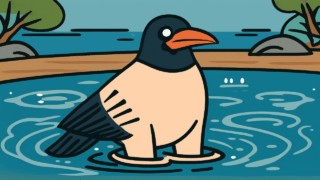 ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ 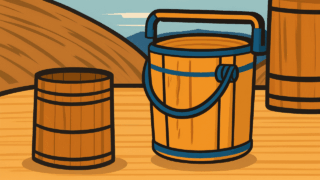 ことわざ
ことわざ 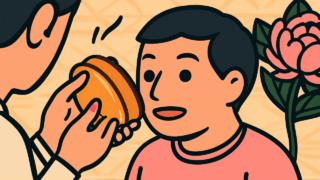 ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ 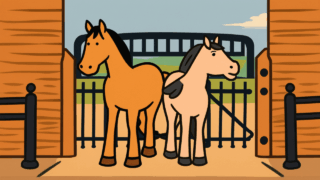 ことわざ
ことわざ