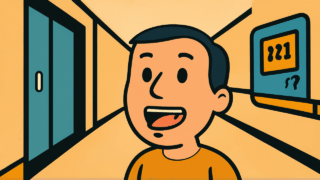 ことわざ
ことわざ 人の口に戸は立てられぬの意味・由来・使い方|日本のことわざ解説
人の口に戸は立てられぬの読み方ひとのくちにとはたてられぬ人の口に戸は立てられぬの意味「人の口に戸は立てられぬ」は、人々の話や噂を止めることはできないという意味です。人の口は常に開いており、物理的な戸で封じることができないように、一度人々の間...
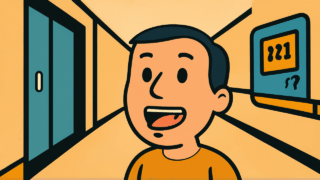 ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ 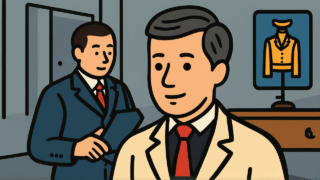 ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ 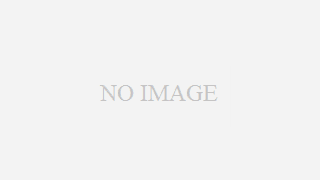 ことわざ
ことわざ 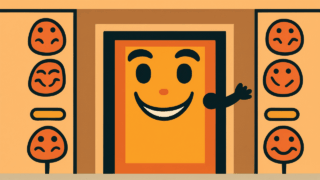 ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ 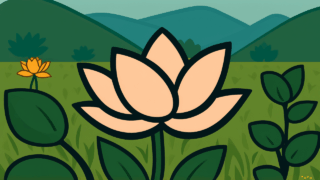 ことわざ
ことわざ