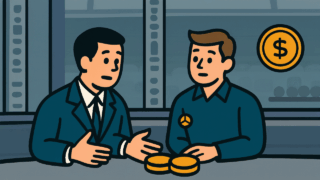 ことわざ
ことわざ 沈黙は金、雄弁は銀の意味・由来・使い方|日本のことわざ解説
沈黙は金、雄弁は銀の読み方ちんもくはきん、ゆうべんはぎん沈黙は金、雄弁は銀の意味このことわざは、「適切な沈黙は雄弁な言葉よりも価値がある」という意味です。つまり、何でもかんでも喋ればいいというものではなく、時には黙っていることの方が、どんな...
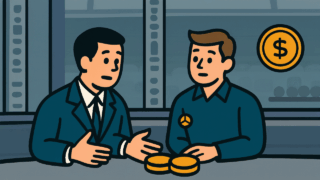 ことわざ
ことわざ 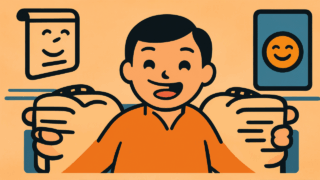 ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ 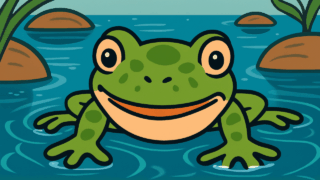 ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ 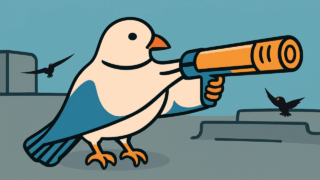 ことわざ
ことわざ 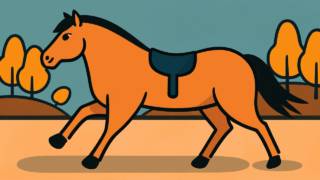 ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ