 ことわざ
ことわざ 知恵は小出しにせよの意味・由来・使い方|日本のことわざ解説
知恵は小出しにせよの読み方ちえはこだしにせよ知恵は小出しにせよの意味「知恵は小出しにせよ」とは、持っている知識や知恵を一度に全て相手に教えるのではなく、相手の理解度や成長段階に応じて段階的に伝えていくべきだという教えです。このことわざは、教...
 ことわざ
ことわざ 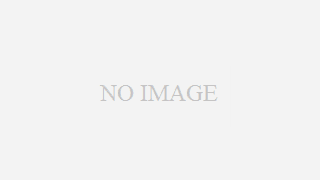 ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ 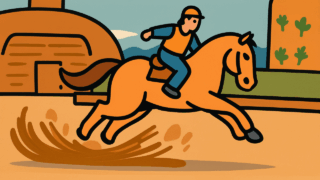 ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ 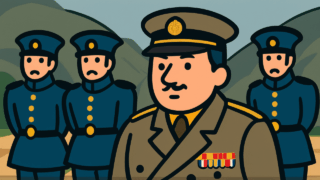 ことわざ
ことわざ 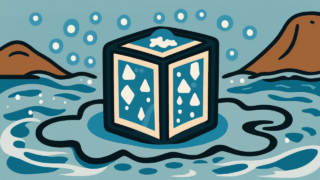 ことわざ
ことわざ