 ことわざ
ことわざ 鹿を逐う者は山を見ずの意味・由来・使い方|日本のことわざ解説
鹿を逐う者は山を見ずの読み方しかをおうものはやまをみず鹿を逐う者は山を見ずの意味「鹿を逐う者は山を見ず」は、目先の利益や欲しいものに夢中になりすぎて、周囲の状況や全体像を見失ってしまうことを戒めることわざです。鹿という獲物に集中するあまり、...
 ことわざ
ことわざ 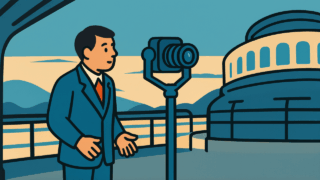 ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ 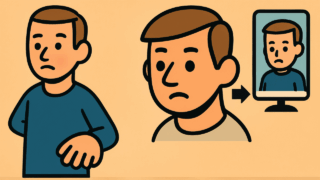 ことわざ
ことわざ 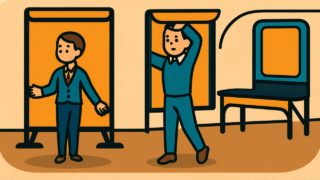 ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ