 ことわざ
ことわざ 終わり良ければすべて良しの意味・由来・使い方|日本のことわざ解説
終わり良ければすべて良しの読み方おわりよければすべてよし終わり良ければすべて良しの意味「終わり良ければすべて良し」は、物事の過程でどんなに困難や失敗があっても、最終的に良い結果になれば、それまでの苦労や問題はすべて報われるという意味です。こ...
 ことわざ
ことわざ 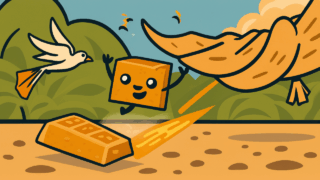 ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ 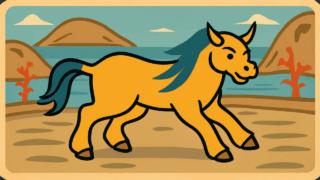 ことわざ
ことわざ 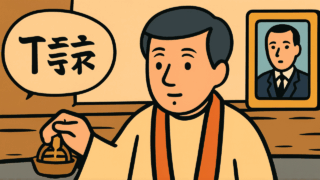 ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ 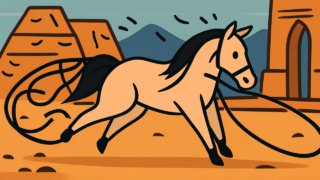 ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ