 ことわざ
ことわざ 酒は百薬の長の意味・由来・使い方|日本のことわざ解説
酒は百薬の長の読み方さけはひゃくやくのちょう酒は百薬の長の意味「酒は百薬の長」とは、適量の酒は多くの薬よりも優れた効果を持つという意味です。この言葉は、酒を大量に飲むことを推奨しているのではありません。むしろ、適度な量の酒が持つ薬効を評価し...
 ことわざ
ことわざ 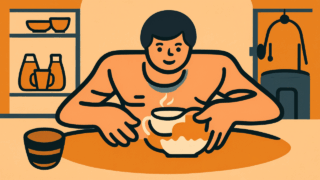 ことわざ
ことわざ 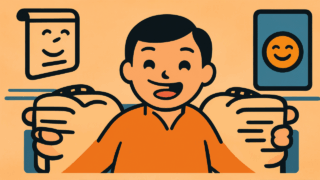 ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ 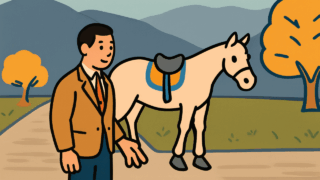 ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ 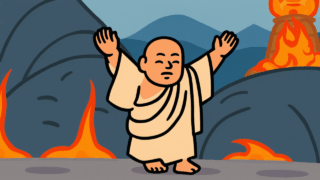 ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ