 ことわざ
ことわざ 提灯に釣鐘の意味・由来・使い方|日本のことわざ解説
提灯に釣鐘の読み方ちょうちんにつりがね提灯に釣鐘の意味「提灯に釣鐘」は、つり合いが取れないほど差が大きすぎて、比較にならないことを表すことわざです。軽くて安価な提灯と、重くて高価な釣鐘では、重さも価値も格も全く違いすぎて、同じ土俵で比べるこ...
 ことわざ
ことわざ 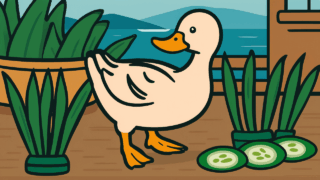 ことわざ
ことわざ 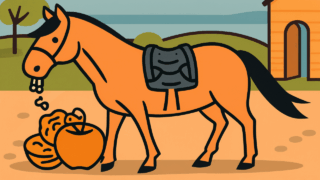 ことわざ
ことわざ 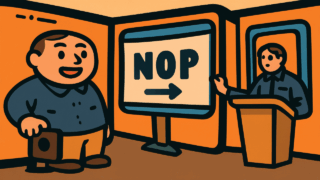 ことわざ
ことわざ 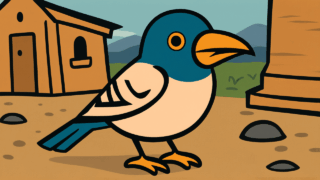 ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ 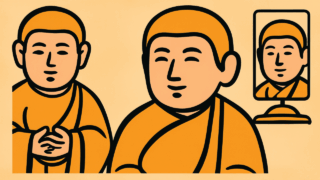 ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ 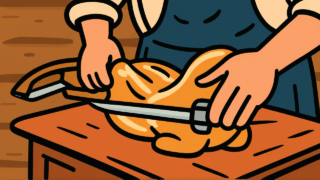 ことわざ
ことわざ