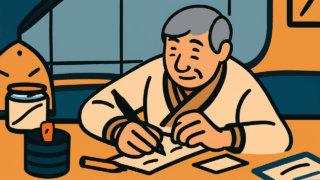 ことわざ
ことわざ 六十の手習いの意味・由来・使い方|日本のことわざ解説
六十の手習いの読み方ろくじゅうのてならい六十の手習いの意味「六十の手習い」は、年を取ってから新しいことを学び始めることを表すことわざです。このことわざは、高齢になってから学習を始めることの価値を肯定的に捉えた表現です。「手習い」とは文字の読...
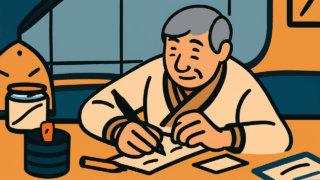 ことわざ
ことわざ 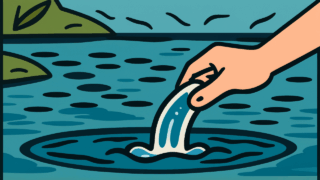 ことわざ
ことわざ 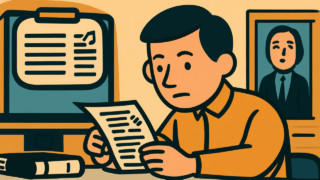 ことわざ
ことわざ 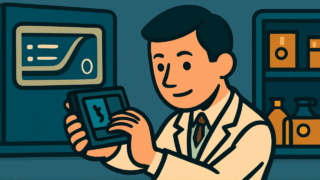 ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ 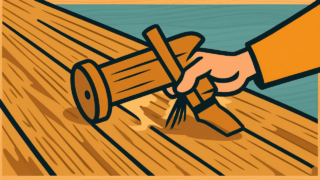 ことわざ
ことわざ 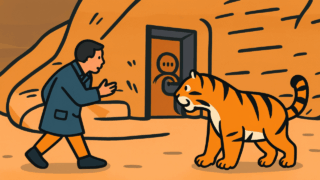 ことわざ
ことわざ 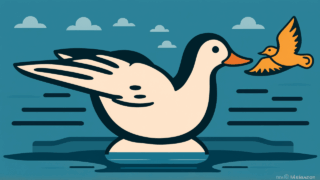 ことわざ
ことわざ