 ことわざ
ことわざ 花の下より鼻の下の意味・由来・使い方|日本のことわざ解説
花の下より鼻の下の読み方はなのしたよりはなのした花の下より鼻の下の意味「花の下より鼻の下」は、風流や美的な楽しみよりも、実際の生活に必要な食べ物の方が大切だという意味です。美しい桜の花の下で過ごす優雅な時間も素晴らしいものですが、それよりも...
 ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ 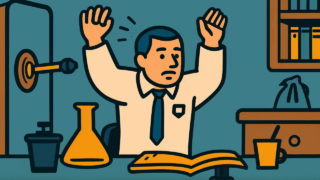 ことわざ
ことわざ 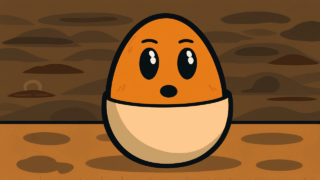 ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ 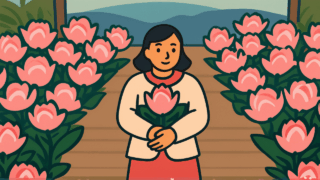 ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ 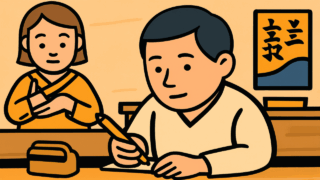 ことわざ
ことわざ