 ことわざ
ことわざ 猿に烏帽子の意味・由来・使い方|日本のことわざ解説
猿に烏帽子の読み方さるにえぼし猿に烏帽子の意味「猿に烏帽子」とは、その人の身分や能力に不相応な地位や装いをすることで、かえって滑稽に見えてしまうことを表します。このことわざは、外見だけを取り繕っても本質は変わらないという深い意味を持っていま...
 ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ 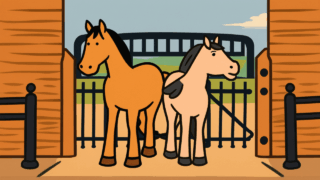 ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ 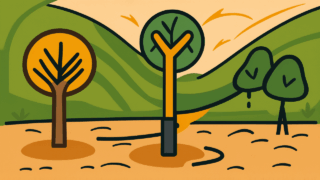 ことわざ
ことわざ 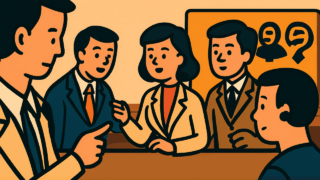 ことわざ
ことわざ 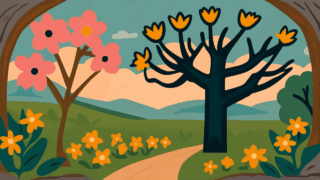 ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ