 ことわざ
ことわざ 好いた事はせぬが損の意味・由来・使い方|日本のことわざ解説
好いた事はせぬが損の読み方すいたことはせぬがそん好いた事はせぬが損の意味このことわざは「正しいことや良いことをしないでいると、結局は自分が損をすることになる」という意味です。ここでの「好いた事」は現代語の「好きなこと」ではなく、「良いこと」...
 ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ 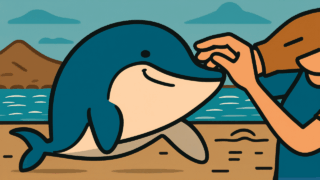 ことわざ
ことわざ 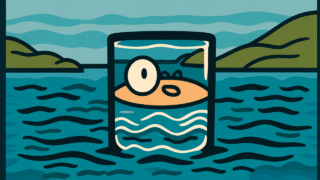 ことわざ
ことわざ 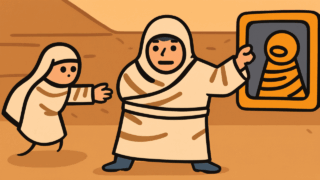 ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ 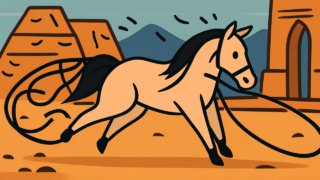 ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ