 ことわざ
ことわざ 親が死んでも食休みの意味・由来・使い方|日本のことわざ解説
親が死んでも食休みの読み方おやがしんでもしょくやすみ親が死んでも食休みの意味このことわざは、食事の後の休憩(食休み)は、どんなに緊急事態が起きても必ず取るべきだという意味です。親が亡くなるという人生最大の緊急事態でさえも、食後の消化時間だけ...
 ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ 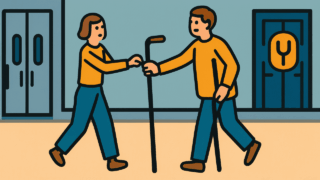 ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ