すまじきものは宮仕えの読み方
すまじきものはみやづかえ
すまじきものは宮仕えの意味
「すまじきものは宮仕え」とは、他人に仕えて働くことの辛さや理不尽さを表現したことわざです。
このことわざは、雇われて働く立場の人が直面する様々な困難を的確に表現しています。上司や組織の方針に従わなければならず、時には自分の信念や考えと相反することでも受け入れざるを得ない状況を指しているのです。理不尽な命令を受けても反論できない立場の辛さ、成果を上げても正当に評価されない不満、人間関係の複雑さに巻き込まれる苦痛など、雇用関係における様々な問題を包括的に表現した言葉なのです。
現代でも、サラリーマンや公務員など、組織に属して働く多くの人々が共感できる内容でしょう。自分の裁量で自由に決められることが少なく、常に上からの指示や組織の都合に左右される立場の大変さを、簡潔に言い表した智恵の言葉として親しまれています。
由来・語源
「すまじきものは宮仕え」の由来は、平安時代の宮廷文化にまで遡ります。「すまじき」は古語で「すべきでない」「避けるべき」という意味を持ち、「宮仕え」は朝廷や貴族の家で働くことを指していました。
この表現が生まれた背景には、平安時代から鎌倉時代にかけての宮廷社会の複雑な人間関係があります。当時の宮仕えは、表面的には名誉ある職業とされていましたが、実際には主君の気まぐれに振り回され、派閥争いに巻き込まれ、常に立場の不安定さに悩まされる生活でした。
特に、平安後期から武家社会への転換期において、宮廷での地位は以前ほどの実権を持たなくなり、形式的な役職に留まることが多くなりました。それでも生活のために宮仕えを続けなければならない人々の心境が、このことわざに込められているのです。
文献では、鎌倉時代の随筆や軍記物語にこの表現の原型が見られ、室町時代には現在の形で定着したと考えられています。長い間、多くの人々が共感してきた言葉だからこそ、現代まで受け継がれているのですね。
豆知識
「宮仕え」という言葉は、もともと天皇や皇族にお仕えすることを指していましたが、時代が下るにつれて大名や武家への奉公も含むようになりました。興味深いのは、江戸時代には「宮仕え」が武士の奉公だけでなく、商家での丁稚奉公まで含む広い意味で使われるようになったことです。
このことわざに使われている「すまじき」という古語は、現代語の「すべきでない」よりもはるかに強い否定の気持ちを表現しています。単なる「やめた方がいい」ではなく、「絶対に避けるべき」という強い忌避感を込めた表現だったのです。
使用例
- 部長の無茶な要求にまた従わされて、本当にすまじきものは宮仕えだと痛感した
- 独立して自分の店を始めた友人を見ていると、すまじきものは宮仕えという言葉が身に染みる
現代的解釈
現代社会において、このことわざは新たな意味を持つようになっています。終身雇用制度が崩れ、働き方の多様化が進む中で、「宮仕え」の概念自体が大きく変化しているのです。
かつては一つの会社に長く勤めることが当たり前でしたが、今では転職やフリーランス、起業という選択肢が身近になりました。そのため、理不尽な職場環境に我慢し続ける必要性は以前ほど高くありません。むしろ、ブラック企業や パワーハラスメントなどの問題が社会的に認知され、労働者の権利意識も向上しています。
一方で、リモートワークやギグエコノミーの普及により、新しい形の「宮仕え」も生まれています。プラットフォーム企業に依存するフリーランスや、複数の会社と契約する働き方では、従来とは異なる制約や理不尽さに直面することもあります。
また、SNSの普及により、職場での不満や理不尽な体験を共有しやすくなり、「宮仕えの辛さ」に対する共感や連帯感も生まれています。現代では、このことわざは単なる愚痴ではなく、働き方を見直すきっかけや、より良い職場環境を求める原動力としても機能しているのです。
AIが聞いたら
江戸時代の武士は「主君のために命を捧げる」という崇高な理想を掲げていたが、実際は上司の機嫌取りや派閥争いに明け暮れていた。現代サラリーマンは「会社の成長に貢献する」という目標を持ちながら、結局は数字に追われ、上司の顔色をうかがう日々を送っている。
興味深いのは、両者とも「理想の高さ」と「現実の泥臭さ」のギャップが極めて大きいことだ。武士は「忠義」という美しい言葉の裏で、実は給料(扶持)をもらうサラリーマンだった。主君が理不尽でも逆らえず、転職も簡単ではない。これは現代の会社員とまったく同じ構造である。
さらに驚くべきは、武士もサラリーマンも「やりがい搾取」の対象だった点だ。武士は「名誉のために働け」と言われ、現代人は「成長のために働け」と言われる。どちらも精神的な報酬で現実的な不満を我慢させられている。
つまり「宮仕え」の本質的な苦しさは、個人の理想と組織の論理が根本的に相容れないことにある。400年前も今も、人は組織の歯車になることの矛盾に悩み続けているのだ。
現代人に教えること
このことわざが現代の私たちに教えてくれるのは、働くことの本質的な意味について考える大切さです。確かに、他人に仕えて働くことには理不尽さや制約がつきものですが、それは決して無意味な苦痛ではありません。
大切なのは、その状況をどう捉え、どう活かすかという視点です。組織の中で働くことで得られる経験、人間関係、スキルは、あなた自身の成長につながる貴重な財産となります。理不尽な状況に直面した時こそ、問題解決能力や忍耐力、コミュニケーション能力が鍛えられるのです。
また、現代では働き方の選択肢が広がっています。「すまじき宮仕え」だからといって永遠に我慢し続ける必要はありません。スキルを磨き、人脈を築き、より良い環境を求めて行動することも大切な選択です。
このことわざは、働くことの現実を受け入れながらも、その中で自分らしさを失わず、前向きに歩んでいく知恵を教えてくれています。あなたの今の状況がどんなに大変でも、それは必ず次のステップへの糧となるはずです。


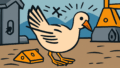
コメント