好いた事はせぬが損の読み方
すいたことはせぬがそん
好いた事はせぬが損の意味
このことわざは「正しいことや良いことをしないでいると、結局は自分が損をすることになる」という意味です。
ここでの「好いた事」は現代語の「好きなこと」ではなく、「良いこと」「正しいこと」「道理にかなったこと」を指しています。つまり、やるべき正しい行いを怠ったり、面倒だからと避けたりしていると、最終的には自分に不利益が返ってくるという教訓なのです。
この表現は、目先の楽や利益を優先して、本来すべき正しい行いを怠る人への戒めとして使われます。例えば、人への親切を面倒がったり、約束を守らなかったり、誠実な対応を怠ったりする場面で用いられるでしょう。
現代でも、正直な商売をしない店が結局客を失ったり、人間関係で誠実さを欠いた人が孤立したりする状況は珍しくありません。このことわざは、そうした「正道を歩まないことの代償」を端的に表現した、実に的確な人生の指針と言えるでしょう。
由来・語源
「好いた事はせぬが損」の由来について、明確な文献的根拠は定かではありませんが、江戸時代の庶民の間で生まれた実用的な教訓として広まったと考えられています。
この表現の興味深い点は、「好いた事」という古語の使い方にあります。現代では「好きなこと」と解釈されがちですが、江戸時代の「好いた事」は「良いこと」「適切なこと」「道理にかなったこと」という意味で使われていました。つまり、個人的な嗜好ではなく、客観的に見て正しい行為を指していたのです。
江戸時代の商人社会では、目先の利益にとらわれず、長期的な信頼関係を築くことが重要視されていました。そうした背景から、「一見面倒に思える正しい行い」を怠ることの愚かさを戒める言葉として定着したのでしょう。
また、「損」という言葉も、単なる金銭的な損失だけでなく、人としての品格や信用を失うという、より深い意味での損失を表していたと推測されます。このことわざは、短期的な楽を求めて正道を外れることの危険性を、庶民の知恵として言い表した表現だったのです。
使用例
- あの人は挨拶もろくにしないから、好いた事はせぬが損で誰からも相手にされなくなった
- 正直に報告するのが面倒だったが、好いた事はせぬが損というから、きちんと話しておこう
現代的解釈
現代社会において、このことわざは新たな重要性を帯びています。情報化社会では、一つの不誠実な行為が瞬時に拡散され、長期的な信用失墜につながるリスクが格段に高まっているからです。
SNSやオンラインレビューが普及した今、企業や個人の評判は以前にも増して透明化されています。「面倒だから適当に対応する」「正しい手続きを省略する」といった行為は、すぐに露見し、デジタル上に永続的な記録として残ってしまいます。これは江戸時代の商人が恐れた「信用失墜」が、現代ではより深刻な形で現実化していることを意味します。
一方で、現代では「効率性」や「合理性」が重視される傾向があり、「正しいことだが時間のかかる行為」が軽視されがちです。しかし、テクノロジーの発達により、長期的な視点での「正しい行い」の価値がより明確に数値化されるようになりました。顧客満足度、従業員エンゲージメント、ESG投資など、誠実な行動が具体的な利益として測定可能になっているのです。
このことわざの教えは、現代のビジネス倫理やコンプライアンス重視の流れとも合致しており、むしろ古い時代よりも切実な意味を持っているかもしれません。
AIが聞いたら
機会費用とは「何かを選んだ時に、諦めた選択肢から得られたであろう最大の利益」のことです。たとえば、アルバイトをせずに勉強を選んだ場合、稼げたはずの時給1000円が機会費用になります。
「好いた事はせぬが損」は、この機会費用の概念を驚くほど正確に表現しています。やりたいことを我慢して別の選択をした時、実は目に見えない大きな損失が発生しているという洞察です。
現代の行動経済学研究では、人は「やったことの後悔」より「やらなかったことの後悔」の方を長期間引きずることが分かっています。ハーバード大学の調査によると、75歳以上の高齢者の76%が「挑戦しなかったこと」を最も後悔していると答えました。
つまり、好きなことを諦める選択は、単に楽しみを失うだけでなく、将来の満足度や成長機会、人脈形成など、計算できない多くの価値を放棄することになります。
江戸時代の人々は、経済学用語を知らずとも、人生における真の「コスト」を直感的に理解していたのです。現代人が複雑な数式で表現する概念を、わずか10文字で的確に表現した先人の知恵には驚かされます。好きなことへの投資こそが、最も確実なリターンを生む投資なのかもしれません。
現代人に教えること
このことわざが現代の私たちに教えてくれるのは、「正しさへの投資」という考え方です。正しい行いは時に面倒で、すぐには報われないように感じるかもしれません。しかし、それは将来の自分への最も確実な投資なのです。
現代社会では、短期的な成果や効率性が重視されがちですが、本当に大切なのは長期的な信頼関係です。あなたが今日示した誠実さは、明日のあなたを支える基盤となります。挨拶を欠かさない、約束を守る、相手の立場を考える。こうした当たり前のことを当たり前に続けることが、実は最も賢い生き方なのかもしれません。
「面倒だな」と感じた時こそ、このことわざを思い出してください。その一歩が、あなたの人生を豊かにする種となるはずです。正しいことを選ぶ勇気を持つあなたは、きっと多くの人から愛され、信頼される人になるでしょう。そして何より、鏡に映る自分を心から誇らしく思えるはずです。

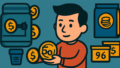

コメント