将を射んとせば先ず馬を射よの読み方
しょうをいんとせばまずうまをいよ
将を射んとせば先ず馬を射よの意味
このことわざの本来の意味は、「大きな目標を達成するためには、まずその基盤となる重要な要素から攻略せよ」ということです。
直接的に本丸を攻めるのではなく、まずはその力の源となっている重要な支えを断つことで、最終的な目標達成をより確実にするという戦略的思考を表しています。これは決して遠回りではなく、むしろ最も効率的で確実な方法だという教えなのです。
ビジネスの場面では、競合他社に勝つために、まずは優秀な人材を引き抜いたり、重要な取引先との関係を築いたりすることに当てはまります。また、学習においても、難しい問題に挑戦する前に基礎をしっかり固めることの重要性を示しています。
この表現を使う理由は、人は往々にして目立つ目標ばかりに目を奪われ、その土台となる重要な要素を見落としがちだからです。真の成功者は、表面的な華やかさではなく、本質的な力の源泉を見抜く洞察力を持っているということを、このことわざは教えてくれているのです。
由来・語源
このことわざは、中国の古典『史記』に記された故事に由来しています。漢の高祖劉邦に仕えた名将・韓信が、敵将を討ち取る際の戦術として語った言葉が元になっているとされています。
古代中国では、将軍は戦場で馬に乗って指揮を執るのが常でした。馬は将軍にとって単なる移動手段ではなく、戦場での生命線そのものだったのです。敵の将軍を直接狙うのは困難でも、まず愛馬を射ることで将軍の行動を封じ、結果的に将軍を無力化できるという戦術的な発想から生まれました。
この故事が日本に伝わったのは、おそらく平安時代から鎌倉時代にかけてと考えられています。武士の時代になると、日本でも馬上での戦いが重要視されるようになり、この教えは戦術論として広く受け入れられました。江戸時代には武士の教養として定着し、やがて一般庶民の間でも「目標達成のための効果的な手順」という意味で使われるようになったのです。
現代まで受け継がれているこのことわざは、単なる戦術論を超えて、物事を成し遂げるための知恵として愛され続けています。
豆知識
古代中国の戦場では、将軍の愛馬は単なる乗り物以上の存在でした。名馬は現在の高級車以上の価値があり、一頭で小さな村が買えるほどの財産だったのです。そのため、馬を失うことは経済的打撃も大きく、将軍の戦意を大きく削ぐ効果があったと考えられています。
日本の戦国時代でも同様で、武将たちは愛馬に名前をつけ、家族同然に大切にしていました。織田信長の愛馬「治部少輔」や上杉謙信の「放生月毛」など、歴史に名を残す名馬も数多く存在します。
使用例
- 新規事業を成功させたいなら、将を射んとせば先ず馬を射よで、まずは業界のキーパーソンとの関係作りから始めよう
- 受験勉強も将を射んとせば先ず馬を射よの精神で、いきなり過去問に挑戦せず基礎固めを徹底することにした
現代的解釈
現代社会において、このことわざの意味はより複層的で戦略的なものになっています。情報化社会では「馬」に当たる重要な要素が多様化し、その見極めがより困難になっているのです。
ビジネスの世界では、企業の「馬」はもはや単一の要素ではありません。優秀な人材、技術力、ブランド力、資金力、情報ネットワークなど、複数の重要な支柱が存在します。成功する経営者は、競合他社のどの「馬」を狙うべきかを的確に判断し、戦略的にアプローチしています。
SNSやデジタルマーケティングの時代では、インフルエンサーや口コミの影響力が「馬」の役割を果たすことも多くなりました。商品やサービスを直接宣伝するより、まず信頼できる発信者との関係を築くことが、結果的に大きな成果につながるのです。
一方で、現代では「馬を射る」行為が倫理的に問題視される場面も増えています。人材の引き抜きや取引先の奪い合いは、時として不正競争として批判されることもあります。このことわざの知恵を活用する際は、フェアプレーの精神を忘れずに、建設的な競争を心がけることが重要でしょう。
また、個人のキャリア形成においても、このことわざは新しい意味を持っています。理想の職業に就くために、まずは必要なスキルや人脈という「馬」を育てることの重要性が、これまで以上に認識されているのです。
AIが聞いたら
SNSインフルエンサーにとっての「馬」はフォロワー数やエンゲージメント率です。どんなにカリスマ性があっても、アルゴリズムに嫌われて投稿が表示されなくなれば一瞬で影響力を失います。実際、2021年にInstagramのアルゴリズム変更で、多くの有名インフルエンサーのリーチが70%以上減少したケースが報告されています。
政治家の「馬」は資金源とメディア露出です。スキャンダルで大口献金者が離れたり、メディアから無視されるようになると、政策の良し悪しに関係なく政治生命が絶たれます。企業経営者なら、株主の信頼や主力取引先との関係が「馬」に当たるでしょう。
興味深いのは、現代の「馬」は複数存在し、しかも相互に関連していることです。例えば、ある企業のCEOを標的にする場合、株価を下げる→機関投資家の信頼を失う→取締役会での発言力が低下する、という連鎖反応を狙えます。
さらに現代特有なのは、「馬」が見えにくくなっていることです。昔の将軍の馬は誰の目にも明らかでしたが、今は権力者が何に最も依存しているかを見抜くのに高度な分析力が必要です。SNSの裏側のアルゴリズム、複雑な資本関係、見えないネットワーク効果など、真の「馬」を特定できる者だけが現代の戦略的優位を握れるのです。
現代人に教えること
このことわざが現代の私たちに教えてくれるのは、「急がば回れ」の精神と「本質を見抜く目」の大切さです。SNSで瞬時に情報が拡散し、すべてがスピード勝負に見える現代だからこそ、立ち止まって「本当に重要なものは何か」を考える時間が必要なのです。
あなたが今、何かの目標に向かって頑張っているなら、一度足を止めてみてください。その目標を支えている「馬」は何でしょうか。資格取得が目標なら基礎学力、転職が目標なら人脈やスキル、良い関係を築きたいなら相手への理解かもしれません。
大切なのは、その「馬」を攻撃的に奪うのではなく、自分自身の中に育てることです。他人の成功を妬むより、自分の土台を固める。派手な成果を求めるより、地道な努力を積み重ねる。そんな姿勢こそが、このことわざが現代に伝えたいメッセージなのです。
遠回りに見える道が、実は最も確実で美しい道のりだということを、きっとあなたも実感できるはずです。


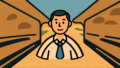
コメント