鯱立ちも芸のうちの読み方
しゃちだちもげいのうち
鯱立ちも芸のうちの意味
「鯱立ちも芸のうち」とは、たとえ下手な芸や単純な技であっても、芸の一つとして認められるという意味です。高度な技術や洗練された技芸だけが価値あるものではなく、たとえ初歩的であったり、未熟であったりしても、それを披露する行為自体に意味があるという考え方を示しています。
このことわざは、芸事や技能の世界で、完璧さや高度さだけを求めるのではなく、多様な表現や試みを受け入れる寛容な姿勢を表しています。使用場面としては、初心者の拙い演技や、まだ磨かれていない技能を温かく受け止める際に用いられます。また、自分の未熟さを謙遜しながらも、挑戦する姿勢を示す時にも使われることがあります。
現代では、完成度の高さばかりが評価される傾向がありますが、このことわざは、どんな芸も最初は未熟であり、その過程にも価値があることを教えてくれます。
由来・語源
このことわざの由来については、明確な文献上の記録が残されていないようですが、言葉の構成要素から興味深い考察ができます。
「鯱立ち」とは、水中で頭を下にして逆立ちする動作を指します。鯱は想像上の生き物として知られていますが、ここでは実際にこの動作を行う海の生き物、つまりイルカやクジラなどの行動を指していると考えられています。これらの生き物が水面から飛び出したり、逆立ちしたりする様子は、古くから人々の目を楽しませてきました。
江戸時代には大道芸や見世物が盛んで、曲芸師たちが様々な技を披露していました。その中には高度な技術を要するものもあれば、比較的単純な技もあったでしょう。鯱立ちのような逆立ちの芸は、派手さはあるものの、熟練の曲芸と比べれば基本的な技の一つだったと推測されます。
しかし、たとえ基本的な技であっても、それを披露することで観客を楽しませることができれば、立派な芸として認められました。このことわざは、そうした芸能の世界における寛容な評価の姿勢を表現したものと考えられています。完璧でなくとも、何かを成し遂げようとする姿勢そのものに価値を見出す、日本の文化的な寛容さが反映されているのかもしれません。
使用例
- 彼の漫才はまだ荒削りだけど、鯱立ちも芸のうちというし、舞台に立つ経験が大切だよ
- 初めての発表で緊張したけれど、鯱立ちも芸のうちと思って堂々とやってみた
普遍的知恵
「鯱立ちも芸のうち」ということわざには、人間社会における寛容さと成長への理解という、深い普遍的な知恵が込められています。
なぜ人は未熟なものを認めることが難しいのでしょうか。それは、私たちが常に完璧さを求め、結果だけを評価しがちだからです。しかし、どんな名人も最初は初心者でした。どんな素晴らしい芸も、最初は拙いものだったのです。このことわざが長く語り継がれてきたのは、人間の成長には必ず未熟な段階があり、その段階を認めることの大切さを、先人たちが深く理解していたからでしょう。
人は誰しも、自分の未熟さを恥じる気持ちと、それでも挑戦したいという欲求の間で揺れ動きます。完璧でなければ価値がないと思い込んでしまえば、人は新しいことに挑戦できなくなってしまいます。このことわざは、そんな人間の心理を見抜き、「完璧でなくても良い、まずは一歩を踏み出すことに意味がある」という励ましを与えてくれます。
また、このことわざは見る側の寛容さについても教えています。他者の未熟さを批判するのではなく、その挑戦する姿勢を認める。そうした温かい眼差しがあってこそ、人は成長できるのです。これは時代を超えて変わらない、人間社会の本質的な真理なのです。
AIが聞いたら
人間の脳は「芸」というカテゴリーを無意識に固定化している。たとえば、美しい舞や巧みな曲芸は芸だが、失敗して転ぶことは芸ではない。この境界線は実は絶対的なものではなく、観客の認知スキーマ、つまり「こうあるべき」という頭の中の枠組みによって決まっている。
鯱立ちという逆立ちの芸を考えてみよう。もし演者が偶然バランスを崩して鯱立ちになったとき、観客が「失敗だ」と認識すればそれは失敗のままだ。しかし演者が堂々と繰り返し、あたかも意図的な技であるかのように振る舞えば、観客の脳内では面白い変化が起きる。認知的不協和、つまり「失敗のはずなのに堂々としている」という矛盾を解消するため、脳は自動的にカテゴリーを再編成する。「これは失敗ではなく、新しい形の芸なのだ」と。
心理学者エレノア・ロッシュの研究では、カテゴリーには明確な境界がなく、典型例からの距離で判断されることが分かっている。つまり「芸らしさ」は固定的ではなく、文脈次第で伸び縮みする。鯱立ちが芸になるプロセスは、まさに観客の認知スキーマを演者が書き換える社会的交渉なのだ。価値は客観的に存在するのではなく、見る側の頭の中で構築される。この柔軟性こそが、人間の文化を豊かにする源泉といえる。
現代人に教えること
このことわざが現代の私たちに教えてくれるのは、完璧さへの過度なこだわりを手放す勇気です。SNSで常に他者と比較され、完成度の高いものばかりが評価される今の時代だからこそ、この教えは重要な意味を持ちます。
あなたが何か新しいことを始めたいと思っているなら、最初から上手くできなくても構いません。下手でも、未熟でも、それを表現すること自体に価値があるのです。ブログを書くのも、絵を描くのも、楽器を演奏するのも、最初は誰もが初心者です。その拙い第一歩を踏み出せるかどうかが、成長への分かれ道なのです。
また、他者の挑戦を見る時も、この教えを思い出してください。誰かの未熟な試みを批判するのではなく、その勇気を認める。そうした温かい眼差しが、社会全体の創造性を育てます。
完璧でなくても良い。まずは始めてみる。そして続けてみる。鯱立ちのような単純な技も、繰り返せばいつか洗練された芸になります。あなたの中にある「やってみたい」という気持ちを、どうか大切にしてください。
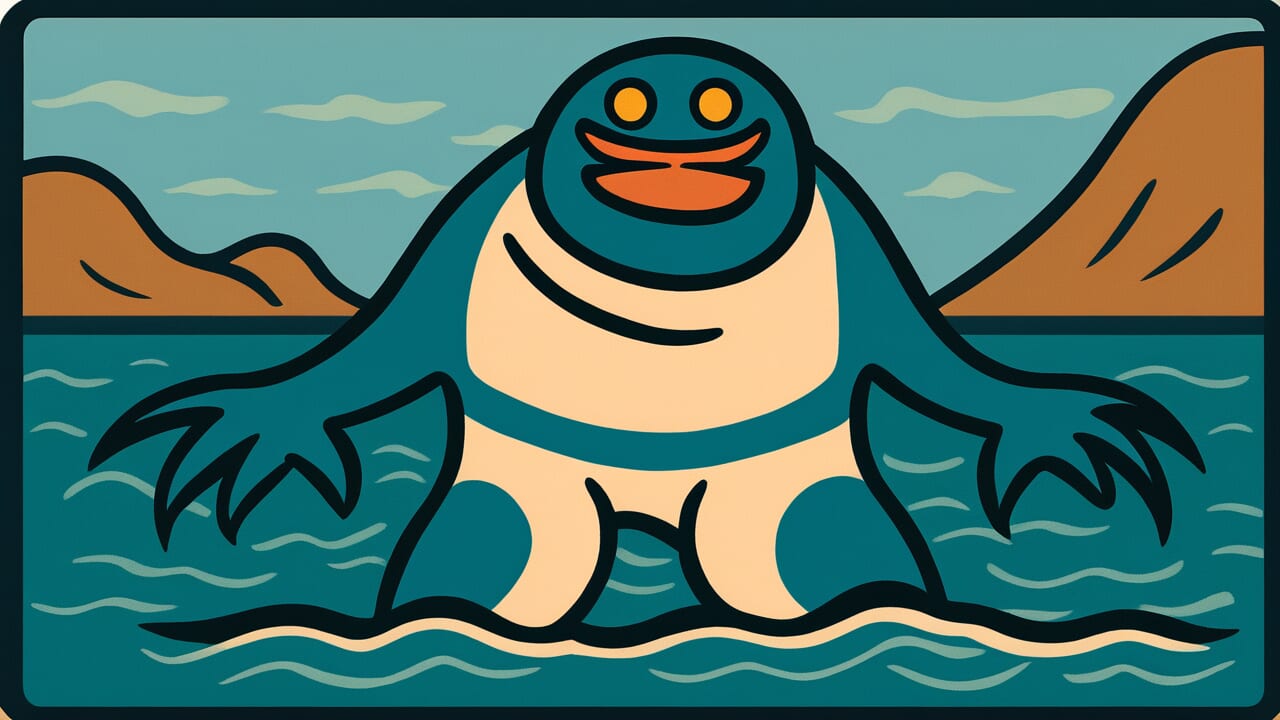


コメント