去る者は日々に疎しの読み方
さるものはひびにうとし
去る者は日々に疎しの意味
「去る者は日々に疎し」は、亡くなった人や離れて行った人への親しみや愛情が、時間の経過とともに自然に薄れていくという人間の心理を表現したことわざです。
これは決して冷たい心を批判しているわけではありません。むしろ、人間の感情の自然な流れを客観的に観察した言葉なのです。どんなに愛していた人でも、その人がいなくなってしまえば、日常生活の中でその人を思い出す機会は徐々に減っていきます。最初は毎日のように思い出していても、やがて週に一度、月に一度となり、ついには特別な日にだけ思い出すようになる。これは人間として当然の心の動きなのです。
このことわざが使われる場面は、主に人の心の移ろいやすさを説明する時です。「あの人のことを忘れるなんて薄情だ」と自分を責める人に対して、「それが人間というものですよ」と慰める際にも使われます。また、生前は慕われていた人が、時間が経つにつれて忘れられていく現実を受け入れる時の表現としても用いられます。現代でも、この人間心理の普遍性は変わらず、多くの人が共感できる深い洞察を含んだことわざと言えるでしょう。
由来・語源
「去る者は日々に疎し」の由来について、実は明確な文献的根拠は見つかっていないのが現状です。しかし、このことわざの構造や使われている言葉から、その成り立ちを推測することができますね。
まず注目したいのは「去る」という言葉です。古語では「去る」は単に「立ち去る」だけでなく、「死ぬ」という意味でも使われていました。つまり、このことわざは元々、亡くなった人への感情の変化を表現していた可能性が高いのです。
「疎し」という古語も重要なポイントです。現代語の「疎遠」の語源となった言葉で、「親しみが薄れる」「関係が希薄になる」という意味を持ちます。この言葉は平安時代から使われており、人間関係の微妙な変化を表現する際によく用いられていました。
「日々に」という表現からは、時間の経過とともに徐々に変化していく様子が読み取れます。これは人間の心理の自然な動きを観察した、非常に現実的な表現と言えるでしょう。
このことわざが生まれた背景には、日本人の人間関係に対する繊細な観察眼があったと考えられます。特に、別れや死別といった避けられない人生の出来事に対して、感情の変化を冷静に見つめる文化的な土壌があったからこそ、このような表現が生まれたのではないでしょうか。
使用例
- 父が亡くなって三年、最初は毎日思い出していたのに、最近はふとした時にしか思い浮かばなくなった、去る者は日々に疎しとはよく言ったものだ
- 転校した親友のことを思い出すのも月に一度程度になってしまい、去る者は日々に疎しを実感している
現代的解釈
現代社会において、「去る者は日々に疎し」はより複雑な意味を持つようになりました。SNSやデジタル技術の発達により、物理的に離れた人ともつながり続けることが可能になったからです。
インスタグラムやフェイスブックでは、遠く離れた友人の日常を毎日のように見ることができます。LINEやメッセージアプリを使えば、いつでも連絡を取り合えるでしょう。これらの技術は、このことわざが前提としていた「距離=疎遠」という図式を根本から変えてしまいました。
しかし興味深いことに、デジタルでつながっていても、実際の関係性は薄れていくケースが多く見られます。SNSで「いいね」を押し合う関係は続いていても、本当に深い話をすることはなくなっている。これは新しい形の「疎し」と言えるかもしれません。
また、現代では転職や引っ越しが頻繁になり、人間関係の流動性が高まっています。職場の同僚との関係も、退職と同時に急速に薄れることが多いでしょう。リモートワークの普及により、物理的な距離がさらに人間関係に影響を与えるようになりました。
一方で、このことわざの本質である「時間とともに感情が薄れる」という人間の心理は、テクノロジーが発達しても変わりません。むしろ情報過多の現代では、一つ一つの人間関係に向ける注意力が分散され、より早く「疎し」の状態になる傾向があるのかもしれませんね。
AIが聞いたら
SNSが普及した現代では、このことわざの構造そのものが逆転現象を起こしている。従来は物理的距離=心理的距離だったが、今や両者は完全に分離した。
最も興味深いのは「接触頻度の逆説」だ。同じ職場や学校にいても、SNSでつながっていない相手とは急速に疎遠になる一方、海外に住む友人とは毎日のようにメッセージを交わし、むしろ関係が深まることがある。物理的な「去る」行為が、デジタル空間では無意味になったのだ。
さらに注目すべきは「選択的親密性」の誕生である。SNSでは自分が関わりたい人だけを選んで接触できるため、物理的に近い人々(近所の住人、同僚など)との偶発的な関係が希薄化する。結果として、目の前にいる人が最も「疎い」存在になりうる。
この現象は脳科学的にも説明できる。人間の脳は「最近接触した情報」を重要視するため、SNSで頻繁にやり取りする遠方の友人の方が、たまにしか話さない隣人よりも心理的に近く感じられる。つまり「去る者は日々に疎し」は「つながらない者は日々に疎し」へと変化し、物理的距離という概念自体が時代遅れになったのである。
現代人に教えること
このことわざは、私たちに人間らしさを受け入れることの大切さを教えてくれます。愛する人への気持ちが時間とともに薄れていくことを、罪悪感を持って受け止める必要はないのです。
現代社会では、SNSで過去の関係を維持し続けることが美徳とされがちですが、すべての人間関係を同じ濃度で保ち続けることは現実的ではありません。むしろ、自然な感情の流れに身を任せることで、今目の前にいる人たちとより深い関係を築くことができるでしょう。
大切なのは、薄れていく感情を否定するのではなく、それも含めて人間の心の自然な動きとして受け入れることです。そうすることで、過去への執着から解放され、現在の人間関係により多くのエネルギーを注げるようになります。
また、このことわざは相手の立場からも考えさせてくれます。自分が誰かの記憶から薄れていくことも自然なことだと理解できれば、より軽やかに人生を歩んでいけるはずです。永遠に覚えていてもらおうとするのではなく、今この瞬間の関係を大切にする。そんな生き方こそが、本当の意味で豊かな人間関係を育むのではないでしょうか。

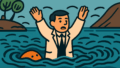
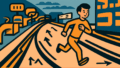
コメント