盗人猛々しいの読み方
ぬすびとたけだけしい
盗人猛々しいの意味
「盗人猛々しい」は、悪いことをした人が、まるで自分が正しいかのように堂々と振る舞ったり、逆に被害者を責めたりする態度を表すことわざです。
このことわざは、道徳的に間違った行為をしておきながら、反省するどころか開き直って威張る人の態度を批判する際に使われます。盗みという明らかな悪行を働いた者が、捕まったり咎められたりした時に、素直に謝罪するのではなく、「自分は悪くない」「相手が悪い」といった態度を取る様子を指しています。
現代でも、不正行為や迷惑行為をした人が、注意されると逆ギレしたり、責任転嫁したりする場面でよく使われます。例えば、ルール違反をして注意された人が「みんなもやっている」と開き直ったり、自分の非を認めずに相手を攻撃したりする時などです。このことわざを使うことで、そうした理不尽で恥知らずな態度への強い非難の気持ちを表現できるのです。
由来・語源
「盗人猛々しい」の由来は、江戸時代の文献に見られる表現が起源とされています。この「猛々しい」という言葉が、現代の理解とは大きく異なる意味を持っていたことが重要なポイントです。
古語の「猛々しい」は、現代語の「図々しい」「厚かましい」という意味ではありませんでした。本来は「勇ましい」「堂々としている」「威勢がよい」という、むしろ肯定的な意味合いを持つ言葉だったのです。つまり「盗人猛々しい」は、「盗人なのに勇ましい」「泥棒のくせに堂々としている」という意味で使われていました。
このことわざが生まれた背景には、江戸時代の社会情勢があります。当時は身分制度が厳格で、盗みを働くような者は社会の最下層に位置していました。そうした立場の人間が、まるで正当な権利を主張するかのように堂々と振る舞う様子を見て、人々は驚きと呆れを込めてこの表現を使ったのでしょう。
言葉の成り立ちとしては、「盗人」という明確に悪い行為をする者と、「猛々しい」という本来は良い意味の言葉を組み合わせることで、その矛盾した状況を強調する効果を生んでいます。時代を経るにつれて「猛々しい」の意味が変化し、現代では「図々しい」という意味で理解されるようになったのです。
豆知識
「猛々しい」という言葉は、現代では「図々しい」という否定的な意味で使われることが多いですが、源氏物語などの古典文学では「美しく勇ましい」という褒め言葉として使われていました。言葉の意味の変遷を示す興味深い例の一つです。
江戸時代の町奉行所の記録によると、実際に捕まった盗人が奉行の前で堂々と弁明する様子がしばしば記録されており、当時の人々にとって「盗人が猛々しい」状況は決して珍しいことではなかったようです。
使用例
- あの人は会社の備品を勝手に持ち帰っておいて、注意されたら逆切れするなんて盗人猛々しいにも程がある
- 不倫がバレた途端に相手を悪者扱いするなんて、まさに盗人猛々しい態度だ
現代的解釈
現代社会では、「盗人猛々しい」が当てはまる場面がより複雑で多様になっています。SNSの普及により、個人の行動が瞬時に拡散される時代において、このことわざが指す行動パターンは以前よりも目立つようになりました。
特に注目すべきは、情報化社会における新しい形の「盗人猛々しさ」です。著作権侵害をしておきながら「みんなやっている」と開き直る人、他人のアイデアを盗用しておいて指摘されると「偶然の一致」と主張する人、フェイクニュースを拡散しておいて「自分も騙された被害者」と責任逃れをする人など、デジタル時代特有の問題が増えています。
また、企業や組織レベルでも、環境破壊や労働問題を起こしておきながら、批判されると「業界全体の問題」「法的には問題ない」と開き直るケースが見られます。これらは現代版の「盗人猛々しい」行為と言えるでしょう。
一方で、現代では被害者の声が届きやすくなったことで、このような理不尽な態度に対する社会の目も厳しくなっています。「盗人猛々しい」行為は、以前よりも早く、より広範囲に批判を受けるようになりました。このことわざは、現代においても人々の正義感を表現する重要な言葉として機能し続けています。
AIが聞いたら
現代心理学の研究で「DARVO」という現象が注目されている。これは「Deny(否定)、Attack(攻撃)、Reverse Victim and Offender(被害者と加害者を逆転させる)」の略で、加害者が自分を被害者に仕立て上げる心理メカニズムだ。驚くべきことに、「盗人猛々しい」はまさにこの現象を完璧に表現している。
心理学者レオン・フェスティンガーが提唱した「認知的不協和理論」によると、人は自分の行動と価値観が矛盾すると強い不快感を覚える。たとえば「自分は良い人」と思っているのに悪いことをした場合、この矛盾を解消するため、無意識に「相手が悪い」「仕方なかった」と自分を正当化する。
実際の研究では、詐欺師の約70%が「被害者にも落ち度があった」と主張し、暴力事件の加害者の60%以上が「先に挑発された」と証言するという。これらは現代の「盗人猛々しい」そのものだ。
さらに興味深いのは、この心理は無意識に働くことが多い点だ。加害者は演技ではなく、本気で自分が被害者だと信じ込んでいる場合が多い。江戸時代の人々は、この複雑な人間心理を「猛々しい」という一言で見抜いていた。現代のSNSでの炎上騒動でも、この古典的パターンが繰り返されている。
現代人に教えること
「盗人猛々しい」ということわざは、私たちに自己反省の大切さを教えてくれます。誰でも間違いを犯すものですが、その時の対応が人としての品格を決めるのです。
現代社会では、SNSなどで自分の行動が多くの人に見られる機会が増えました。だからこそ、間違いを犯した時こそ、その人の真価が問われます。開き直るのではなく、素直に非を認め、改善に努める姿勢が求められているのです。
また、このことわざは他人を見る時の視点も与えてくれます。誰かが「盗人猛々しい」態度を取っていても、その背景には恐れや不安があるかもしれません。批判するだけでなく、なぜそのような態度を取るのかを理解しようとする心の余裕も大切です。
最も重要なのは、自分自身が同じような態度を取っていないか、定期的に振り返ることです。人は誰でも自分を正当化したくなるものですが、時には一歩引いて客観的に自分を見つめ直す勇気が必要なのです。

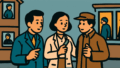
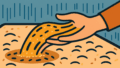
コメント