見ざる聞かざる言わざるの読み方
みざるきかざるいわざる
見ざる聞かざる言わざるの意味
「見ざる聞かざる言わざる」は、道徳に反することや人の悪口、よくないことは見ない、聞かない、言わないという自制の教えを表しています。
これは単なる現実逃避ではなく、むしろ積極的な人格修養の方法なのです。悪いものに心を向けることで自分自身が汚れてしまうことを防ぎ、清らかな心を保つための知恵として生まれました。特に他人の過ちや醜い部分を見聞きしても、それを口外せず、自分の心にも留めないことで、人間関係の調和を保つという実用的な意味もあります。現代でも、ネガティブな情報に振り回されず、建設的なことに意識を向けることの大切さを教えてくれる、非常に実践的な人生訓として理解されています。
由来・語源
「見ざる聞かざる言わざる」の由来は、日光東照宮の神厩舎(しんきゅうしゃ)に彫られた三猿の彫刻で広く知られていますが、実はこの教えの起源はもっと古く、中国の古典にまで遡ります。
最も有力な説として、中国の『論語』の「非礼勿視、非礼勿聴、非礼勿言、非礼勿動」(礼にあらざれば視るなかれ、礼にあらざれば聴くなかれ、礼にあらざれば言うなかれ、礼にあらざれば動くなかれ)という孔子の教えが元になったとされています。これは道徳に反することは見るな、聞くな、言うな、行うなという意味でした。
日本には平安時代頃に仏教とともに伝来し、天台宗の教えの中で「見ざる聞かざる言わざる」として定着しました。猿が用いられるようになったのは、「去る」という言葉と「猿」の音が同じことから、災いが去るという縁起の良い意味が込められたためです。江戸時代には庶民の間でも広く親しまれ、現在のことわざとして定着していきました。
豆知識
日光東照宮の三猿の彫刻には実は8面の猿の彫刻があり、「見ざる聞かざる言わざる」は人間の一生を表現した物語の幼少期の部分にあたります。他の彫刻では猿が成長し、恋をして、結婚し、子育てをする様子が描かれているのです。
三猿のポーズをよく見ると、左から「見ざる」「聞かざる」「言わざる」の順番になっていますが、これは悪いことを見て、それを聞いて、最後に口に出すという、人間の行動パターンを逆から戒めた順序だと考えられています。
使用例
- 職場の噂話には見ざる聞かざる言わざるを心がけている
- SNSの炎上騒ぎは見ざる聞かざる言わざるで関わらないのが一番だ
現代的解釈
現代社会において「見ざる聞かざる言わざる」は、情報過多の時代における自己防衛の知恵として新たな意味を持っています。SNSやインターネットでは24時間、ネガティブなニュースや他人の批判、炎上騒ぎなどが絶え間なく流れてきます。これらすべてに反応していては、精神的な健康を保つことは困難です。
一方で、現代では「見て見ぬふり」「聞こえないふり」として、社会問題や不正に対する無関心を正当化する誤った使い方も見られます。本来の教えは道徳に反することを避けるという意味でしたが、現代では正義感や社会的責任を放棄する口実として使われることもあるのです。
しかし、デジタルデトックスやマインドフルネスといった現代的な概念と照らし合わせると、このことわざの本質的な価値が再認識されています。意図的に有害な情報から距離を置き、建設的なことに集中するという姿勢は、現代人にとって必要不可欠なスキルとなっています。情報を選択的に受け取る能力こそが、現代版「見ざる聞かざる言わざる」の実践と言えるでしょう。
AIが聞いたら
現代人は1日に約3万4千もの決断を迫られているという研究があります。その多くが「この情報を受け取るか、無視するか」という選択です。ここで「見ざる聞かざる言わざる」が、まったく新しい意味を持ちます。
従来は「都合の悪いことから目を逸らす消極的な態度」と捉えられがちでしたが、実は「情報の洪水から自分を守る高度な技術」だったのです。たとえば、SNSで炎上している話題をあえて見ない、根拠不明なニュースを聞き流す、不確実な情報を拡散しない。これらは現代版の三猿そのものです。
心理学の「認知負荷理論」によると、人間の脳が一度に処理できる情報量には限界があります。つまり、すべての情報を受け入れようとすると、本当に大切な判断ができなくなってしまうのです。
興味深いのは、情報を「積極的に遮断する人」ほど、創造性や集中力が高いという研究結果です。現代の成功者たちが「デジタルデトックス」を実践するのも、この原理と同じ。三猿の教えは、実は情報社会を生き抜く最先端のライフハックだったのです。
古い知恵が、まさか現代のメンタルヘルス対策になるとは驚きです。
現代人に教えること
「見ざる聞かざる言わざる」が現代人に教えてくれるのは、情報との付き合い方の知恵です。すべての情報に反応する必要はなく、自分の心の平安と成長にとって本当に必要なものを選択する力を身につけることが大切なのです。
特に現代では、意図的に「見ない」「聞かない」「言わない」選択をすることが、かえって積極的な生き方につながります。ネガティブな情報に時間を奪われるより、自分の目標や大切な人との関係に集中する方が、はるかに豊かな人生を送れるでしょう。
ただし、これは社会的責任を放棄することではありません。本当に必要な時には声を上げ、行動することも大切です。要は、エネルギーを注ぐべきところを見極める判断力を養うことなのです。毎日の小さな選択の積み重ねが、心穏やかで充実した人生を作り上げていくのですね。
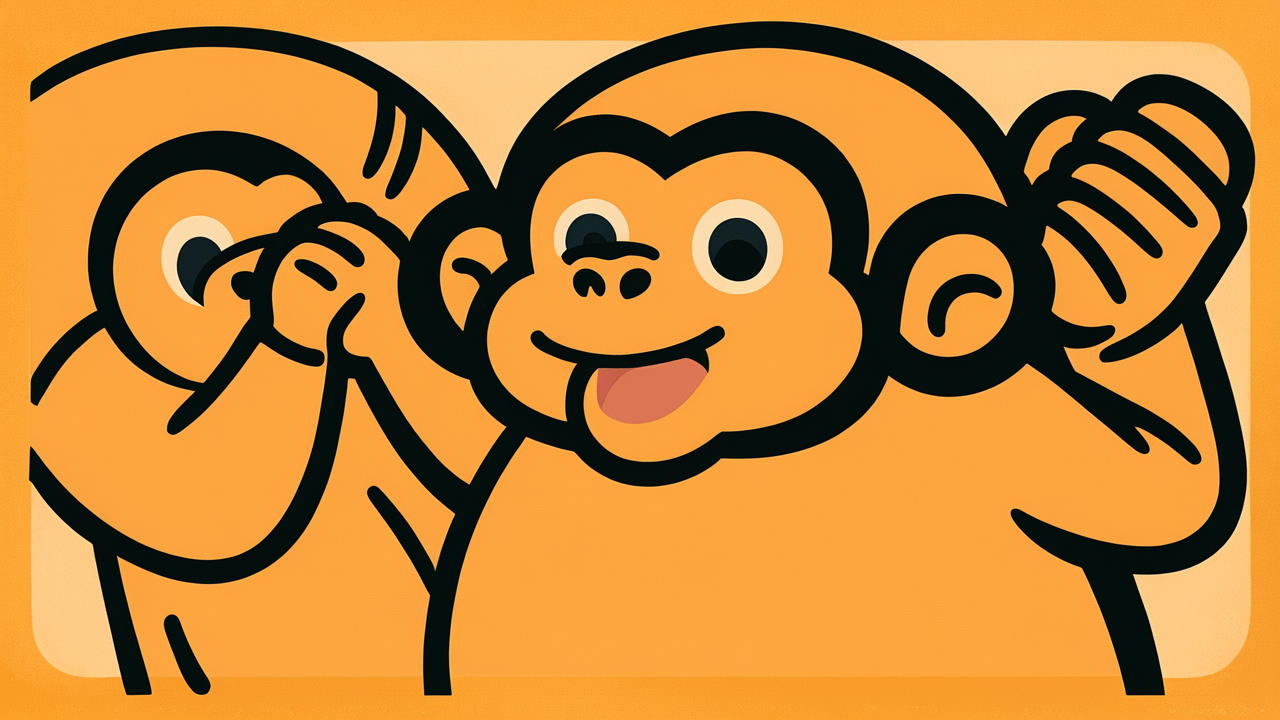

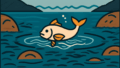
コメント