事が延びれば尾鰭が付くの読み方
ことがのびればおひれがつく
事が延びれば尾鰭が付くの意味
「事が延びれば尾鰭が付く」とは、時間が経つにつれて話が大げさになったり、事実と異なる内容が付け加わっていくことを意味します。
ある出来事が起こった直後は、事実に近い形で語られていた話も、時間が経過して人から人へと伝わるうちに、いつの間にか誇張された表現が加わったり、本来なかった要素が混ざり込んだりします。まるで魚の体に尾鰭が付いているように、話の本体に余計な部分がくっついていく様子を表現しているのです。
このことわざは、噂話や伝聞について語る場面でよく使われます。「あの話、事が延びれば尾鰭が付くから、最初はもっと単純な出来事だったはずだ」というように、話の信憑性を疑う文脈で用いられることが多いですね。現代でも、SNSで情報が拡散される過程で内容が変化していく現象など、まさにこのことわざが示す状況は日常的に見られます。
由来・語源
このことわざの由来について、明確な文献上の記録は残されていないようですが、言葉の構成要素から興味深い考察ができます。
「尾鰭」とは、魚の尾とひれのことです。魚の本体に対して、尾やひれは後から付いている部分ですね。この言葉が比喩的に使われるようになったのは、話に余計な内容が付け加わる様子を、魚の体に尾鰭が付いている姿に重ね合わせたからだと考えられています。
「事が延びれば」という部分も重要です。「延びる」とは時間が経過することを意味します。つまり、出来事が起こってから時間が経てば経つほど、という時間的な要素を強調しているのです。
江戸時代の庶民文化の中で、噂話や世間話が娯楽の一つだった時代背景も関係していると思われます。人から人へと話が伝わる過程で、話し手が面白おかしく脚色したり、聞き手の記憶違いで内容が変わったりする現象は、昔から日常的に観察されていたのでしょう。
魚という身近な生き物の特徴を使って、人間社会の普遍的な現象を的確に表現したこのことわざは、日本人の観察眼の鋭さと言語センスの豊かさを示していると言えるでしょう。
使用例
- 最初は小さなトラブルだったのに、事が延びれば尾鰭が付くで、今では大事件みたいに語られている
- あの噂も事が延びれば尾鰭が付くから、本当のところは当事者に直接聞いた方がいいよ
普遍的知恵
「事が延びれば尾鰭が付く」ということわざは、人間のコミュニケーションに潜む根源的な性質を見抜いています。
なぜ話は時間とともに変化していくのでしょうか。それは人間が単なる情報の伝達装置ではなく、感情や想像力を持つ存在だからです。話を聞いた人は、自分なりに解釈し、記憶し、そして語り直します。その過程で、無意識のうちに自分の感情や価値観が混ざり込み、記憶の曖昧な部分は想像で補われていくのです。
さらに、人には話を面白くしたいという欲求があります。平凡な出来事をそのまま伝えるより、少し劇的に語った方が聞き手の関心を引けますよね。この心理が働くことで、話は自然と膨らんでいきます。
このことわざが長く語り継がれてきたのは、情報の変質という現象が時代を超えた普遍的なものだからです。古代の口承文化でも、現代のインターネット社会でも、情報が人を介して伝わる限り、この法則は変わりません。先人たちは、人間社会における情報の流れには必ず「歪み」が生じることを経験的に理解し、それを魚の姿という見事な比喩で表現したのです。この知恵は、情報との向き合い方について深い示唆を与えてくれます。
AIが聞いたら
情報理論の創始者クロード・シャノンは、情報が伝達される過程で必ずノイズが混入することを数学的に証明しました。重要なのは、このノイズが単純に足し算で増えるのではなく、掛け算で増幅していく点です。たとえば元の情報の正確さが90パーセントだとしても、5人を経由すると0.9の5乗で約59パーセントまで低下します。さらに人間の脳は情報の欠損部分を自動的に補完する性質があるため、この補完された部分が次の人にとっての「元情報」になってしまいます。
この現象を情報エントロピーで見ると、より本質が見えてきます。エントロピーとは情報の不確実性を表す指標ですが、伝達経路が長くなるほど、受け手が推測で埋める部分の自由度が増えていきます。つまり可能性の空間が広がるのです。10通りの解釈ができる情報が次の段階で各10通りに分岐すれば、2段階で100通り、3段階で1000通りになります。これが尾鰭の正体です。
デジタル通信では誤り訂正符号を使ってこの問題を防ぎますが、人間のコミュニケーションには検証機能がありません。時間が経つほど検証の機会も失われ、ノイズだけが純粋培養されていく。このことわざは情報劣化の不可逆性を、科学が証明する何百年も前から言い当てていたのです。
現代人に教えること
このことわざが現代人に教えてくれるのは、情報との賢い付き合い方です。
まず大切なのは、時間が経った話や、何人もの人を経由した情報には、必ず変質が起きていると認識することです。これは疑い深くなれという意味ではなく、情報の性質を理解した上で適切に判断しようということです。重要な情報ほど、できるだけ一次情報源に近いところで確認する習慣を持ちましょう。
また、自分自身が情報の伝達者になるときの責任も考えさせられます。あなたが誰かから聞いた話を別の人に伝えるとき、無意識のうちに「尾鰭」を付けていないでしょうか。事実と推測を区別し、正確に伝えようとする姿勢が大切です。
SNS時代の今、このことわざの教えはより重要性を増しています。シェアボタン一つで情報は瞬時に広がりますが、その前に一呼吸置いて、内容の正確性を確認する習慣を持ちたいものです。
情報が溢れる社会だからこそ、このことわざが示す知恵を活かして、事実を大切にする姿勢を持ち続けることが、あなた自身の信頼性を高めることにもつながるのです。
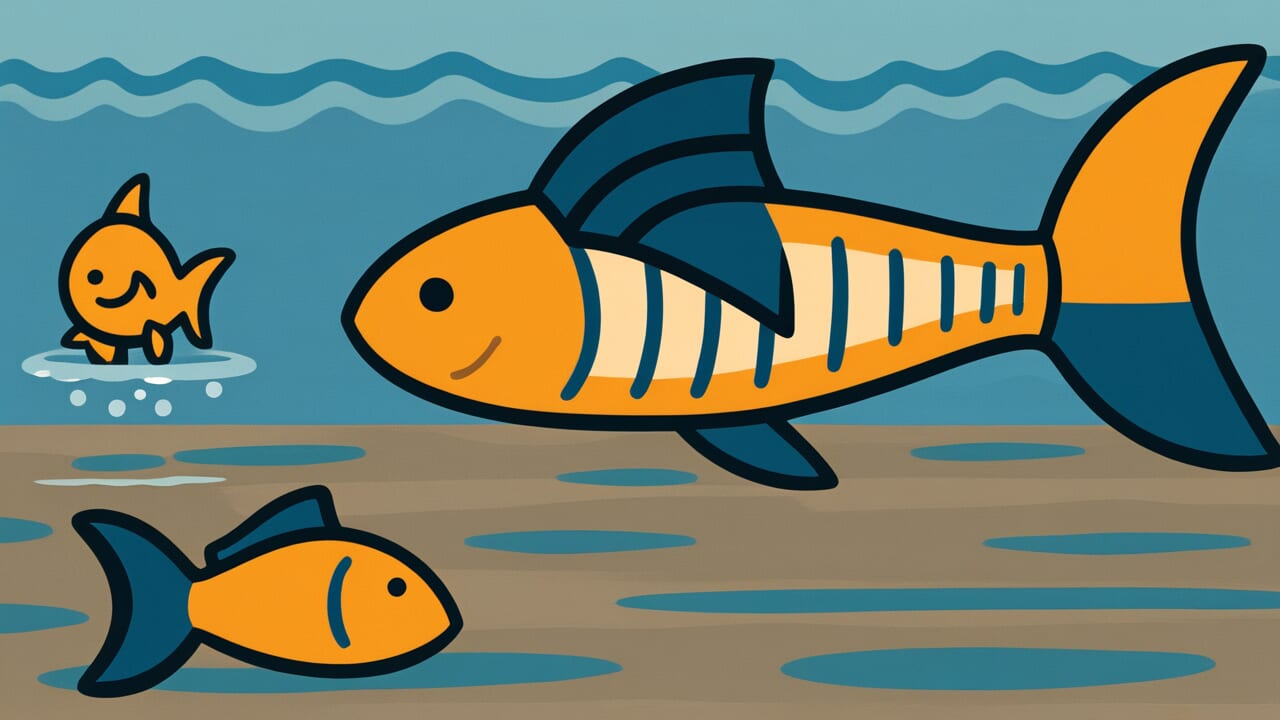


コメント