子養わんと欲すれども親待たずの読み方
こやしなわんとほっすれどもおやまたず
子養わんと欲すれども親待たずの意味
このことわざは、親孝行をしたいと思っても、親が亡くなってしまえば手遅れであるという意味です。子どもが経済的にも精神的にも余裕ができて、ようやく親に恩返しができると思った時には、すでに親はこの世にいないという人生の皮肉を表しています。
若い頃は自分のことで精一杯で、親のありがたみに気づかないものです。しかし、年を重ねて人生経験を積むと、親がどれほど自分を大切に育ててくれたかが分かってきます。そして「今度こそ親孝行をしよう」と思った時には、もう親は高齢になっていたり、すでに亡くなっていたりするのです。
このことわざは、後悔する前に今すぐ行動すべきだという戒めとして使われます。親が元気なうちに感謝の気持ちを伝え、できる限りのことをしておくべきだと教えてくれる言葉なのです。
由来・語源
このことわざは、中国の古典的な教えに由来すると考えられています。特に儒教の思想、中でも孝行を重んじる教えの影響を強く受けているとされています。
「子養わんと欲すれども親待たず」という表現は、漢文調の格調高い言い回しです。「養わんと欲す」は「養いたいと思う」という意味で、「待たず」は「待ってくれない」ということを表しています。この文体自体が、中国の古典から日本に伝わった教訓であることを示唆しています。
日本では江戸時代以降、儒教思想が庶民の間にも広く浸透していく中で、親孝行の大切さを説く言葉として定着していったと考えられます。当時の平均寿命は現代よりもはるかに短く、親を早くに亡くす経験は多くの人にとって身近なものでした。そのため、この言葉は単なる道徳的教訓ではなく、実感を伴った切実な警句として人々の心に響いたのでしょう。
似た意味を持つ言葉として「親孝行したい時には親はなし」という表現もありますが、こちらは平易な日本語で同じ教訓を伝えています。「子養わんと欲すれども親待たず」の方がより古風で格調高い表現として、書物や教訓を説く場面で用いられてきました。
使用例
- 父が入院したと聞いて、子養わんと欲すれども親待たずという言葉が頭をよぎった
- まだ若いからと先延ばしにしていたら、子養わんと欲すれども親待たずになってしまうぞ
普遍的知恵
このことわざが語る真理は、人間の成長と時間の流れの残酷なすれ違いです。私たちは経験を積んで初めて、多くのことの価値に気づきます。親のありがたみも、その一つなのです。
若い頃、私たちは自分の世界を広げることに夢中です。学業、友人関係、恋愛、キャリア。それらすべてが輝いて見え、親の存在は当たり前の背景のように感じられます。親の小言はうるさく、親の心配は過保護に思えるものです。
しかし人生の荒波を経験し、自分自身が誰かを支える立場になって初めて、親がどれほどの愛情と犠牲を注いでくれていたかが分かります。その時になって「ああ、あの時もっと優しくすればよかった」「もっと話を聞いてあげればよかった」と気づくのです。
けれども、人間の成長には時間がかかります。そして親もまた、時間とともに老いていきます。この二つの時間軸は、決して同じペースでは進みません。子どもが親の愛に気づく頃には、親はすでに人生の黄昏を迎えているのです。
このことわざは、この普遍的なすれ違いを見事に言い当てています。だからこそ、何百年も前から人々の心に響き続けているのでしょう。
AIが聞いたら
親の老いは、コップから溢れた水のように、決して元には戻らない。これは熱力学第二法則が示す宇宙の根本原理だ。この法則は「エントロピー、つまり無秩序さは必ず増え続ける」と教える。割れた卵が元に戻らないように、若さから老いへの変化も絶対に逆行しない。
興味深いのは、この不可逆性には確率的な必然性があることだ。たとえば部屋を片付けても自然と散らかるのは、物の配置パターンが「整った状態」より「散らかった状態」の方が圧倒的に多いからだ。計算上、整った状態は数百通りでも、散らかった状態は数兆通りある。同じように、人体を構成する細胞や分子も、若く整った状態より老いた状態の方が圧倒的にパターン数が多い。だから老化は確率的に避けられない。
さらに重要なのは、この過程で失われるエネルギーは二度と回収できない点だ。親が子育てに注いだ時間とエネルギーは、熱として宇宙に散逸し、もう取り戻せない。子が恩返ししようとする時、親の生命エネルギーもまた散逸の途中にある。つまり孝行の機会損失は、宇宙の熱死に向かう一方通行の流れそのものなのだ。
「間に合わなかった」という後悔は、実は物理法則への抗議でもある。時間の矢は決して逆を向かない。
現代人に教えること
このことわざが現代の私たちに教えてくれるのは、「今」という時間の尊さです。私たちはつい「いつか」「そのうち」と先延ばしにしてしまいがちですが、その「いつか」が永遠に来ないかもしれないという現実を忘れてはいけません。
現代社会は忙しく、親と離れて暮らす人も多くなりました。仕事や自分の家庭に追われて、実家に顔を出す機会も減っているかもしれません。しかし、だからこそこのことわざの教えは重要なのです。
親孝行は特別なことである必要はありません。電話一本、短いメッセージ、たまの訪問。そうした小さな積み重ねが、後悔のない関係を作ります。完璧な親孝行ができる日を待つのではなく、今できる小さなことから始めることが大切です。
そしてこの教えは、親子関係だけでなく、すべての大切な人間関係に当てはまります。感謝を伝えたい人、大切にしたい人がいるなら、今日がその日です。明日その人がいる保証はどこにもないのですから。後悔より行動を。それがこのことわざの本質的なメッセージなのです。
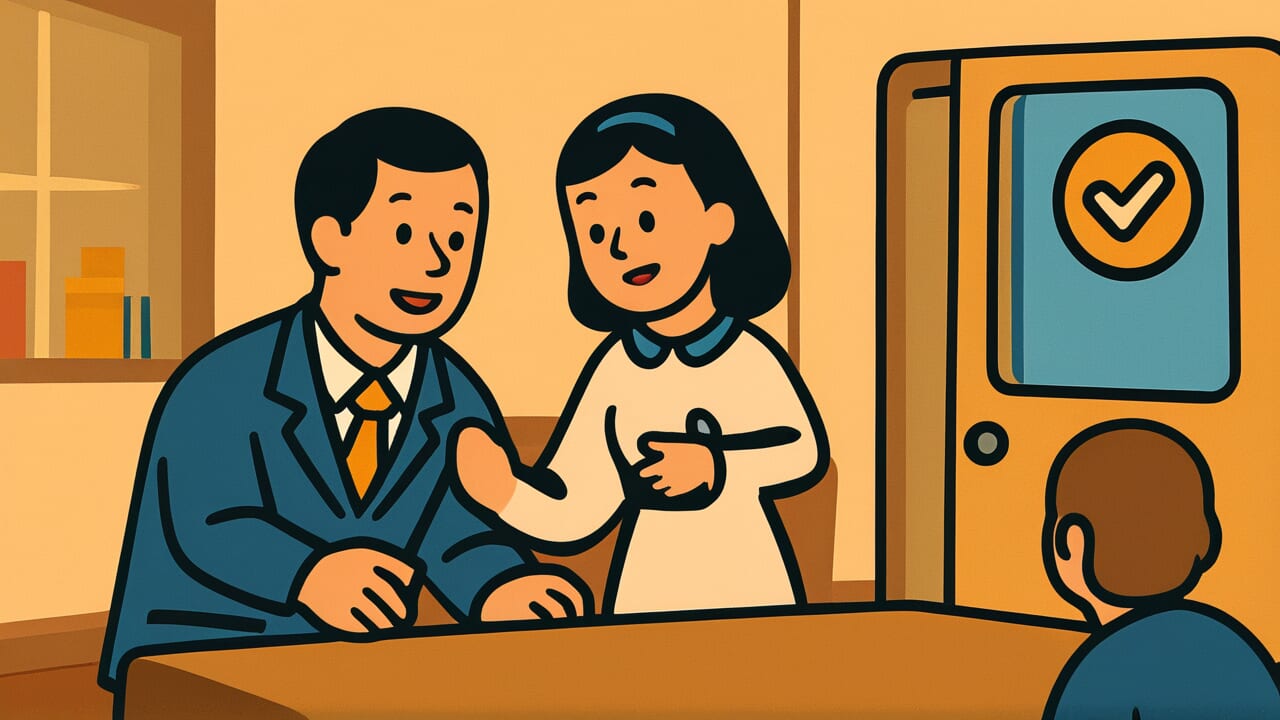


コメント