這えば立て立てば歩めの親心の読み方
はえばたて たてばあゆめのおやごころ
這えば立て立てば歩めの親心の意味
このことわざは、子どもの成長に対する親の際限のない期待と愛情を表現したものです。
赤ちゃんがハイハイをするようになると「早く立ってほしい」と願い、立つようになると「今度は歩いてほしい」と次の段階を望む、そんな親の心境を的確に捉えています。これは決して親のわがままではなく、わが子への深い愛情の表れなのです。
このことわざが使われる場面は、主に子育て中の親同士の会話や、子どもの成長を見守る祖父母の心境を表現する時です。「うちの子もまさに這えば立て立てば歩めの親心で、ついつい次を期待してしまう」といった具合に、親の自然な心理を説明する際に用いられます。
現代でも、この表現は子育て中の親たちに深く共感されています。なぜなら、子どもの成長を願う親心は時代を超えて変わらないものだからです。一つの成長を喜びながらも、同時に次の段階への期待が生まれる、そんな複雑で豊かな親の感情を、このことわざは見事に言い表しているのです。
由来・語源
このことわざの由来は、江戸時代の育児観と深く結びついています。当時の親たちが、わが子の成長を見守りながら自然に口にしていた言葉が、やがて定着したものと考えられています。
「這えば立て」の「這う」は、赤ちゃんがハイハイをする様子を指し、「立てば歩め」の「歩め」は「歩んでほしい」という願いを表現しています。この表現からも分かるように、ことわざの核心は親の心情にあります。
江戸時代の文献を見ると、子どもの成長段階を「這う→立つ→歩く」という順序で捉える表現が多く見られます。これは当時の人々が、子どもの発達を段階的に理解していたことを示しています。医学的知識が限られていた時代でも、親たちは子どもの自然な成長過程を注意深く観察していたのです。
また、このことわざが生まれた背景には、江戸時代の高い乳幼児死亡率があります。多くの子どもが幼くして命を落とす時代だからこそ、わが子が無事に這い、立ち、歩くことへの親の願いは切実でした。そうした時代背景が、この言葉に込められた親心の深さを物語っています。
使用例
- 息子が歩けるようになったと思ったら、今度は走り回ってほしくて、まさに這えば立て立てば歩めの親心だね
- 孫の成長を見ていると、這えば立て立てば歩めの親心で、ついつい次の段階を期待してしまう自分がいる
現代的解釈
現代社会において、このことわざは新たな意味合いを持つようになっています。情報化社会では、子どもの成長に対する親の期待がより多様化し、時として過度になることが問題視されています。
昔は「這う→立つ→歩く」という身体的成長が中心でしたが、現代では「早く話してほしい」「文字を覚えてほしい」「スマートフォンを使えるようになってほしい」など、知的発達への期待が加わっています。さらに、SNSで他の子どもの成長を目にする機会が増えたことで、比較による焦りも生まれやすくなっています。
一方で、発達心理学の知見が広まったことで、「子どもには個人差がある」「急がせすぎてはいけない」という理解も深まっています。現代の親たちは、這えば立て立てば歩めの親心を持ちながらも、それをコントロールする知識も身につけているのです。
教育現場では、このことわざを「適切な期待」について考える材料として使うことがあります。子どもの自然な発達段階を尊重しながら、親としての期待をどう調整するかという現代的な課題に、古いことわざが新しい示唆を与えているのです。
また、現代では子育て支援の文脈でも引用されます。親の期待は自然なものだと認めつつ、それが過度にならないよう見守る姿勢の大切さを伝える際に、このことわざが効果的に使われています。
AIが聞いたら
親の愛情には、深く愛するほど不安が増すという残酷なパラドックスが存在する。このことわざが示すのは、子どもの成長を心から願いながらも、その成長の一歩一歩が新たな心配の種となる矛盾だ。
心理学では「愛着理論」が示すように、強い愛着を持つ親ほど、子どもの安全に対する警戒心が高まる。ハイハイができるようになれば転倒の危険、立てるようになれば高い場所からの落下、歩けるようになれば交通事故や迷子のリスク。愛情の深さが、想像力豊かな「危険予測システム」として機能してしまうのだ。
さらに興味深いのは、この不安が決して解消されないことだ。子どもが大学生になっても、社会人になっても、親の心配は形を変えて続く。つまり親は、愛するがゆえに「完全な安心」という状態に到達できない構造になっている。
これは愛情の本質的な特徴でもある。真の愛とは、相手の幸せを願うと同時に、その相手を失う恐怖と常に隣り合わせの感情なのだ。親心とは、喜びと不安が表裏一体となった、人間の感情の最も複雑で美しい形の一つなのかもしれない。
現代人に教えること
このことわざが現代人に教えてくれるのは、愛情には「今を喜ぶ心」と「未来への期待」の両方が自然に共存するということです。子育てに限らず、私たちは誰かの成長を見守る時、現在の姿を受け入れながらも、さらなる発展を願ってしまうものです。
大切なのは、この気持ちを否定しないことです。部下の成長を願う上司、生徒の向上を望む教師、友人の幸せを祈る気持ち。これらはすべて「這えば立て立てば歩めの親心」と同じ愛情の表れなのです。
現代社会では、期待することが悪いことのように言われがちですが、適切な期待は相手への信頼と愛情の証です。ただし、その期待を押し付けるのではなく、相手のペースを尊重しながら見守る姿勢が重要です。
あなたも誰かの成長を願う時、この親心を思い出してください。今この瞬間の相手を大切にしながら、同時に未来への希望を抱く。その両方があってこそ、真の愛情なのです。期待することを恐れず、でも急かすことなく、温かく見守る心を大切にしていきましょう。


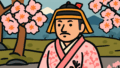
コメント