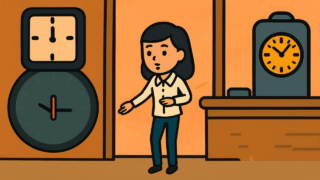 ことわざ
ことわざ 歳月人を待たずの意味・由来・使い方|日本のことわざ解説
歳月人を待たずの読み方さいげつひとをまたず歳月人を待たずの意味「歳月人を待たず」は、時間は人の都合に関係なく、容赦なく過ぎ去っていくという意味です。この言葉は、時の流れの無情さと、それに対する人間の無力さを表現しています。私たちがどんなに「...
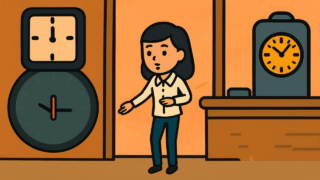 ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ 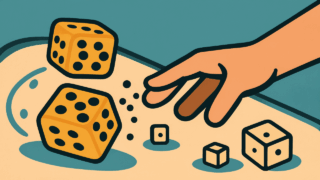 ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ 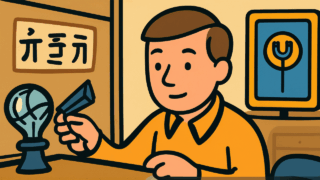 ことわざ
ことわざ