ある時はありがあり、ない時は梨もないの読み方
あるときはありがあり、ないときはなしもない
ある時はありがあり、ない時は梨もないの意味
このことわざは、物事には極端な豊富さと極端な欠乏という両極端があり、中間の状態がないことを表しています。データベースにあるように、ある時はたくさんあるが、ない時は本当に何もないという状況を指す言葉です。
特に好況と不況の波のように、時期によって状況が大きく変動する場面で使われます。景気が良い時には仕事も収入も十分にあるのに、景気が悪くなると仕事も収入も全くなくなってしまう。あるいは、ある商品が流行している時には店頭に山積みされているのに、流行が去ると全く見かけなくなる。そんな極端な変化を表現する時に用いられるのです。
また、物の偏在を表す言葉でもあります。ある場所には必要以上に集まっているのに、別の場所では全く手に入らない。そうした不均衡な分布状況を指摘する際にも使われます。
現代では、市場の需給バランスや経済の循環、資源の分配の不均等さなどを説明する際に、この表現が生きています。
由来・語源
このことわざの由来について、明確な文献上の記録は残されていないようですが、言葉の構造から興味深い特徴が見えてきます。
まず注目したいのは「ありがあり」と「梨もない」という対比です。「ありがあり」は「有りが有り」つまり「あるものがたくさんある」という意味の強調表現ですね。一方の「梨もない」は「無しもない」、つまり「何もない」という完全な欠乏状態を表しています。
この表現の面白さは、単に「ある」と「ない」を対比させるのではなく、「ありがあり」という豊富さの極致と「梨もない」という欠乏の極致を並べている点にあります。中間がない、極端から極端への振れ幅の大きさを強調する構造になっているのです。
このことわざが生まれた背景には、日本の農業社会における収穫の不安定さがあったと考えられています。豊作の年には米も野菜も余るほど手に入るのに、凶作の年には本当に何もかもが不足する。そんな極端な状況の繰り返しを、人々は身をもって経験してきました。
また商業の世界でも、好景気の時には商品が飛ぶように売れ、不景気になると全く売れなくなる。そうした経済活動の波を表現する言葉としても使われてきたと推測されます。
使用例
- あの業界はある時はありがあり、ない時は梨もないから、安定した収入を得るのが難しいんだよね
- コロナ禍でマスクの供給がまさにある時はありがあり、ない時は梨もないという状況だった
普遍的知恵
このことわざが語り継がれてきた理由は、人間社会における普遍的な不安定性を見事に言い当てているからでしょう。私たちは常に「安定」を求めながら、実際には極端な変動の中で生きています。
人間の心理には興味深い特徴があります。豊かな時には、その状態が永遠に続くかのように錯覚してしまうのです。仕事が順調な時、お金がある時、物が豊富にある時、私たちはつい油断してしまいます。逆に、何もない時には、この苦しい状態から抜け出せないのではないかという絶望に襲われます。
しかし、このことわざは冷静に現実を見つめています。「ある時」と「ない時」は、どちらも一時的な状態に過ぎないのだと。波のように、満ち引きを繰り返すのが世の常なのだと教えてくれるのです。
先人たちは、この極端な振れ幅こそが人生の本質だと見抜いていました。自然の恵みも、経済の動きも、人の運も、すべては循環しています。豊かさの中で謙虚さを忘れず、欠乏の中で希望を失わない。そんな心の在り方の大切さを、このことわざは静かに語りかけているのです。
変動することを恐れるのではなく、変動するものだと受け入れる。その覚悟こそが、不確実な世界を生き抜く知恵なのかもしれません。
AIが聞いたら
ネットワーク科学の研究者が発見した驚くべき事実があります。インターネットのリンク構造を調べると、ごく一部のサイトに接続が集中し、大多数のサイトはほとんどリンクされていません。この分布を数式で表すと、リンク数がk本あるサイトの数は、kのマイナス2乗から3乗に比例します。つまり、リンクが10倍になるとサイト数は100分の1から1000分の1になる。これが冪乗則です。
なぜこんな偏りが生まれるのか。答えは「優先的選択」というメカニズムにあります。新しいサイトがリンクを張る時、すでに多くのリンクを持つサイトを選ぶ確率が高い。たとえば論文を書く時、引用数の多い有名論文を引用しがちですよね。この「人気なものがさらに人気になる」プロセスが繰り返されると、数学的に必然的に冪乗分布が現れます。
このことわざの本質は、まさにこの正のフィードバックループです。ある時に梨があれば、それを元手に取引ができ、信用が生まれ、さらに梨が集まる。ない時は取引の機会すら得られず、持っていた信用さえ失う。バラバシ教授の研究チームは、この優先的選択が働くネットワークでは、時間とともに格差が拡大し続けることを数学的に証明しました。SNSのフォロワー数、都市の人口、企業の規模。現代社会の至る所でこの法則が作動しています。
現代人に教えること
このことわざが現代の私たちに教えてくれるのは、極端な変動を前提とした生き方の知恵です。
まず大切なのは、豊かな時の備えです。仕事が順調な時、収入がある時こそ、将来の「ない時」に備えて蓄えておく。これは単なる貯蓄だけでなく、スキルを磨いたり、人間関係を大切にしたり、健康に投資したりすることも含まれます。今あるものが永遠に続くと思わないことが、賢明な生き方なのです。
同時に、このことわざは希望も与えてくれます。今が「ない時」だとしても、それは永遠ではありません。状況は必ず変わります。苦しい時期を耐え抜く力、そして次の「ある時」に備えて準備を続ける姿勢が大切です。
現代社会では、この波の周期がますます短く、振れ幅が大きくなっています。だからこそ、変動することを恐れるのではなく、変動に対応できる柔軟性を身につけることが求められているのです。
あなたの人生にも、きっと波があるでしょう。でも、その波を理解し、上手に乗りこなすことができれば、どんな状況でも前を向いて歩いていけるはずです。
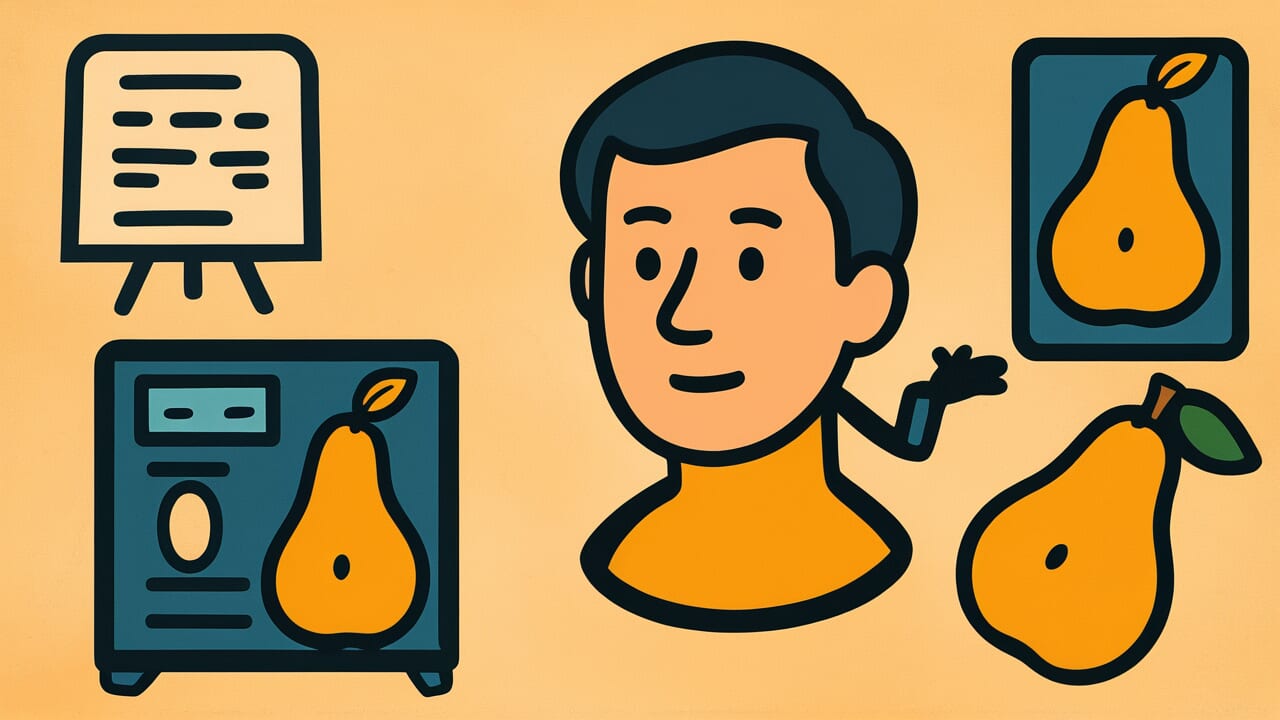


コメント