悪法もまた法なりの読み方
あくほうもまたほうなり
悪法もまた法なりの意味
このことわざは、法律の内容が不当であったり理不尽であったりしても、それが正式に定められた法である以上は従わなければならないという意味を表しています。法治国家においては、個人の判断で法を無視することは許されず、たとえその法が自分にとって不利益であっても遵守する義務があるという考え方です。
この表現が使われるのは、法の内容に疑問を感じながらも、法秩序を維持することの重要性を強調したい場面です。もし各人が自分の判断で法を選択的に守ったり破ったりすれば、社会の秩序は崩壊してしまいます。現代では、法の支配の原則を説明する際や、不本意ながらも規則に従わざるを得ない状況を表現する際に用いられます。ただし、悪法は改正されるべきであり、民主的な手続きによって法を変えていく努力も同時に必要だという含意も持っています。
由来・語源
このことわざは、古代ギリシャの哲学者ソクラテスの最期に関連する言葉として知られています。紀元前399年、ソクラテスは不敬神の罪と青年を堕落させた罪で死刑判決を受けました。彼の弟子たちは脱獄を勧めましたが、ソクラテスは「悪法もまた法なり」という趣旨の言葉を残し、毒杯を仰いで刑に服したと伝えられています。
ただし、この言葉が実際にソクラテスの口から発せられたという確実な記録は、プラトンの対話篇などには見当たらないとされています。むしろ、ソクラテスの行動と思想を後世の人々が解釈し、この言葉として結晶化させたという説が有力です。日本では明治時代以降、西洋哲学の紹介とともに広まったと考えられています。
法の支配という概念が確立していく過程で、この言葉は重要な意味を持つようになりました。たとえ法の内容が不当であっても、法治主義を守ることの重要性を説く文脈で使われてきたのです。同時に、この言葉は法の限界や、悪法を改正する必要性を示唆する警句としても理解されてきました。
使用例
- 駐車違反の罰金は高すぎると思うけど、悪法もまた法なりだから払うしかないな
- 校則に納得できない部分もあるが、悪法もまた法なりで従うべきだという先生の言葉には一理ある
普遍的知恵
「悪法もまた法なり」ということわざが示すのは、人間社会における秩序と正義のジレンマです。私たちは誰もが正義を求めますが、同時に秩序なくして社会は成り立たないという現実に直面します。
このことわざが長く語り継がれてきたのは、人間が集団で生きる限り避けられない根本的な問題を突いているからです。完璧な法律など存在しません。どんな法も、ある人にとっては不公平に感じられるものです。しかし、もし各人が「この法は不当だ」と判断して従わなくなれば、社会は無秩序に陥ります。
ここには深い人間理解があります。人は感情的な生き物であり、自分に不利な決まりには反発したくなるものです。しかし同時に、理性的に考えれば、ルールを守ることで得られる安定と安全の価値も理解できます。このことわざは、その葛藤の中で理性を選ぶことの重要性を説いているのです。
さらに重要なのは、このことわざが単なる服従を説いているわけではないという点です。悪法に従いながらも、それを改正する努力を続けることこそが、成熟した市民の姿勢だと教えています。法を破壊するのではなく、法の枠内で変革を目指す。これは人類が長い歴史の中で学んできた知恵なのです。
AIが聞いたら
悪法に従うべきかという問題は、実はゲーム理論の囚人のジレンマと同じ構造を持っている。各個人が「この悪法は破っても構わない」と判断すると、短期的には自分だけ得をする。たとえば不合理な規制を無視すれば、自分だけ自由に行動できる。しかし全員が同じ判断をすると、法システム全体が崩壊し、誰も法を守らない無秩序状態になる。これは囚人のジレンマで両者が裏切りを選んで最悪の結果になるのと同じだ。
興味深いのは、ここにナッシュ均衡が成立する点だ。ナッシュ均衡とは、他の人の選択を前提にすると、誰も自分の選択を変えたくない状態のこと。もし大多数が悪法でも守ると選択している社会では、自分一人が破っても逮捕されるリスクが高く、従う方が合理的になる。逆に大多数が破っている社会では、法の執行力が弱まり、破る方が合理的になる。つまり悪法への服従は、社会全体の選択によって安定する均衡点なのだ。
さらに数学的に見ると、この均衡には複数のパターンがある。全員が従う均衡と、全員が破る均衡の両方が理論上存在しうる。ソクラテスの言葉は、社会を前者の均衡に保つための戦略的選択だったと解釈できる。一人の違反が連鎖反応を起こして悪い均衡へ移行するのを防ぐため、あえて悪法にも従うという選択をした。これは個人の損得ではなく、システム全体の安定性を優先した高度な戦略的思考だったわけだ。
現代人に教えること
このことわざが現代の私たちに教えてくれるのは、不満を持ちながらも建設的に行動することの大切さです。職場の規則、学校のルール、社会の法律、私たちは日々さまざまな決まりごとの中で生きています。その中には納得できないものもあるでしょう。
しかし、気に入らないからといってすぐに無視したり反発したりするのではなく、まずは従いながら、正当な手続きで変えていく努力をする。これが成熟した態度だとこのことわざは教えています。会社の不合理な規則があれば、上司に提案する。学校の校則に疑問があれば、生徒会で議論する。社会の法律に問題があれば、選挙で意思を示す。
大切なのは、秩序を保ちながら改善を目指すというバランス感覚です。破壊は簡単ですが、建設的な変化には忍耐と知恵が必要です。あなたが今、理不尽だと感じているルールがあるなら、それを変える正当な方法を探してみてください。従いながら変える、この両立こそが、より良い社会を作る力になるのです。
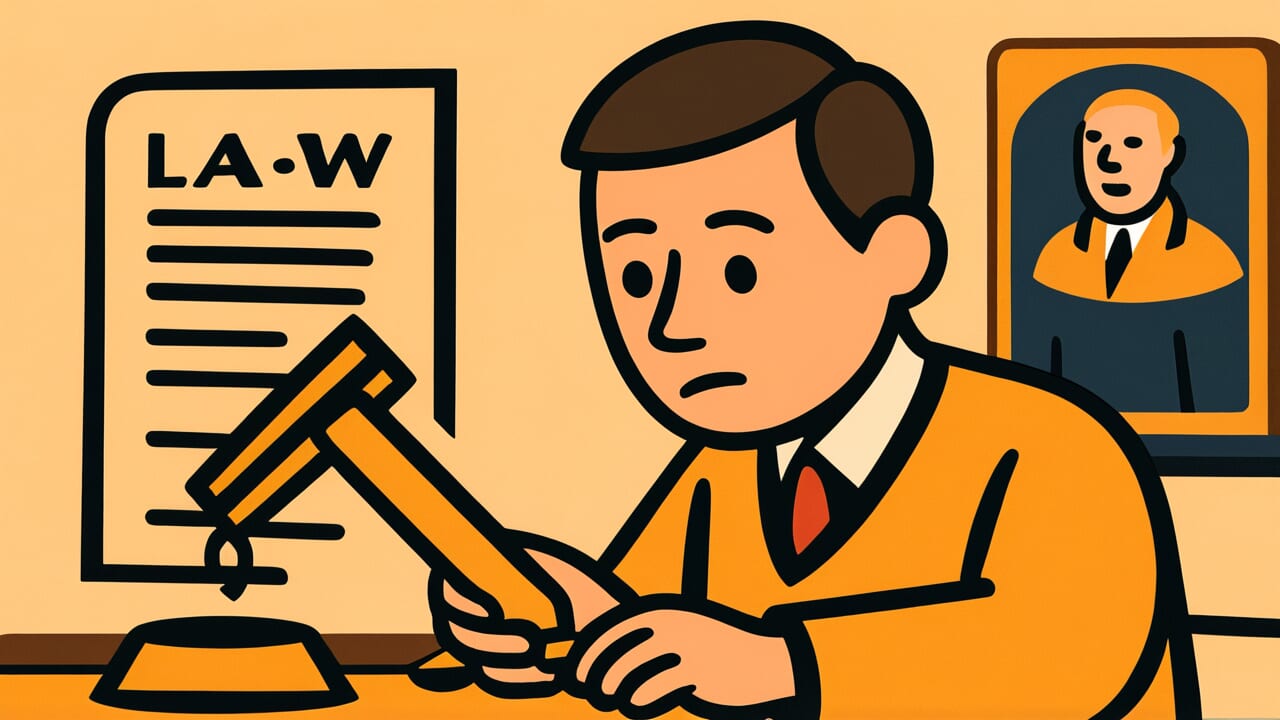


コメント