謀夫孔だ多し、是を用て集らずの読み方
ぼうふこうだおおし、これをもちいてあつまらず
謀夫孔だ多し、是を用て集らずの意味
このことわざは「相談相手や助言者が多すぎると、かえって意見がまとまらず、物事が前に進まない」という意味です。
一見すると、多くの人から知恵を借りることは良いことのように思えますよね。しかし実際には、あまりにも多くの人が意見を出し合うと、それぞれが異なる考えを持っているため、結論を出すのが困難になってしまうのです。「船頭多くして船山に上る」と似た教訓ですが、こちらはより政治的・組織的な場面での意思決定の困難さを表現しています。
このことわざを使う場面は、主に会議や相談事で参加者が多すぎて収拾がつかない状況や、プロジェクトで関係者が増えすぎて方向性が定まらない時などです。現代でも、委員会や企画会議で「謀夫孔だ多し」の状況は頻繁に起こりますね。適切な人数での議論の重要性を説く際に、この古い知恵が今でも生きているのです。
由来・語源
このことわざは、中国の古典『書経』(尚書)の「大禹謨」という章に記されている言葉が由来とされています。「謀夫孔だ多し、是を用て集らず」という表現は、古代中国の政治思想の中で生まれた教訓なのです。
「孔だ」の「孔」は「はなはだ」という意味の古語で、現代語の「非常に」「とても」に相当します。つまり「謀夫」(計画を立てる人、相談役)が「孔だ多し」(非常に多い)という状況を表しているのですね。
この言葉が日本に伝わったのは、中国の古典が仏教とともに伝来した時代と考えられています。平安時代から鎌倉時代にかけて、貴族や僧侶たちの間で漢籍の学習が盛んになり、その過程でこうした政治的な教訓も日本の知識人の間に広まっていったのでしょう。
特に江戸時代になると、朱子学の普及とともに『書経』の研究も本格化し、このことわざも武士階級の教養として定着していきました。組織運営の難しさを端的に表現したこの言葉は、時代を超えて多くの指導者たちに警鐘を鳴らし続けてきたのです。
使用例
- 新商品の企画会議に関係部署全員を呼んだら、謀夫孔だ多しで結局何も決まらなかった
- 町内会の役員を増やしすぎて、謀夫孔だ多しの状態になってしまった
現代的解釈
現代社会では、このことわざの意味がより深刻な問題として浮き彫りになっています。情報化社会の発達により、誰もが簡単に意見を発信できるようになった結果、「謀夫孔だ多し」の状況が日常的に発生しているのです。
特にSNSやオンライン会議の普及により、従来なら参加できなかった人々も議論に加わることができるようになりました。これは民主的で素晴らしいことですが、同時に意見の収束が困難になるという新たな課題も生まれています。企業のリモートワークでは、チャットツールに様々な提案が飛び交い、かえって意思決定が遅れるケースも珍しくありません。
また、現代では「多様性」や「インクルーシブ」という価値観が重視される一方で、効率的な意思決定との間でジレンマが生じています。全員の意見を聞くことは大切ですが、それが組織の機動力を奪ってしまっては本末転倒です。
しかし、このことわざが示す問題への対処法も進化しています。ファシリテーション技術の発達、AI による意見集約システム、段階的な意思決定プロセスなど、多くの知恵を活かしながらも効率的に結論を導く手法が開発されているのです。古い知恵と新しい技術の融合が、現代版の解決策を生み出しているのですね。
AIが聞いたら
現代のビジネス書でよく見かける「会議の参加者は7±2人が理想」という法則は、実は2500年前の中国古典『論語』が既に指摘していた真理だった。「謀夫孔だ多し、是を用て集らず」は、まさに現代企業が陥る「会議地獄」の本質を見抜いている。
心理学者のアーヴィング・ジャニスが提唱した「集団思考」理論によると、参加者が増えるほど個人の責任感は希薄化し、「誰かが決めてくれるだろう」という心理が働く。これは現代の大企業でよく見られる光景そのものだ。20人が参加するプロジェクト会議で、結局誰も明確な決断を下せずに「次回までに検討」で終わる状況は、まさにこのことわざが警告した事態である。
さらに興味深いのは、意見の多様性が必ずしも良い結果を生まないという点だ。現代の組織心理学では「パラドックス・オブ・チョイス」として知られるが、選択肢が多すぎると人は決断を先延ばしにする傾向がある。古代中国の賢人たちは、この人間の本質的な弱さを経験的に理解していたのだ。
現代でも成功している企業の多くは、意思決定プロセスで「少数精鋭主義」を採用している。アマゾンの「2ピザルール」(会議参加者はピザ2枚で足りる人数まで)は、この古典的知恵の現代版実践例と言えるだろう。
現代人に教えること
このことわざが現代人に教えてくれるのは、「質の高い意思決定には、適切な規模と明確な役割分担が必要」ということです。多くの意見を聞くことは大切ですが、それを整理し、方向性を示すリーダーシップも同じように重要なのですね。
現代社会では、あらゆる場面で多様な声に耳を傾けることが求められています。しかし、すべての意見を平等に扱おうとすると、かえって混乱を招いてしまうことがあります。大切なのは、適切なタイミングで適切な人に相談し、最終的には責任を持って決断することです。
あなたが何かを決めるとき、周りの人全員に相談する必要はありません。本当に信頼できる数人の意見を聞き、最後は自分の判断で進む勇気を持ちましょう。完璧な答えを求めすぎず、「今できる最善の選択」を心がけることで、人生はもっとスムーズに進んでいくはずです。
古代中国の知恵が、現代のあなたの背中をそっと押してくれているのかもしれませんね。


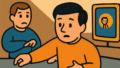
コメント