鳥は木を択べども木は鳥を択ばずの読み方
とりはきをえらべどもきはとりをえらばず
鳥は木を択べども木は鳥を択ばずの意味
このことわざは、優秀な人材は自分が働く場所を選ぶ自由があるのに対し、組織や雇う側はそうした人材を選り好みできる立場にないという意味を表しています。能力のある人は複数の選択肢の中から条件の良い職場を選べますが、受け入れる側は人材不足のため、来てくれる人を断る余裕がないという状況を示しているのです。
この表現は、人材市場における力関係の非対称性を端的に表しています。特に優秀な技能を持つ人や専門性の高い人材ほど、自分の条件に合った環境を求めて移動する自由があります。一方、組織側は常に人材確保に苦労しており、来てくれる人材を歓迎せざるを得ない立場にあるのです。現代でも、人材獲得競争が激しい業界や、専門職の採用場面でこの構図は変わっていません。優秀な人材が主導権を握る雇用市場の現実を、鳥と木という自然の姿に例えた鋭い観察眼が光ることわざです。
由来・語源
このことわざの明確な出典は定かではありませんが、言葉の構造から興味深い考察ができます。「鳥は木を択べども」という前半部分は、鳥が自由に飛び回り、止まる木を選べる様子を表しています。一方「木は鳥を択ばず」という後半は、木が根を張って動けないため、どんな鳥が来ても拒むことができない状態を示しています。
この対比的な構造は、中国の古典に見られる対句表現の影響を受けている可能性があります。日本では古くから、人材と組織の関係を自然界の事象に例える表現が好まれてきました。鳥と木という組み合わせは、移動の自由がある存在とない存在という対照的な関係を分かりやすく示しています。
江戸時代から明治時代にかけて、武士や商人の間で人材の流動性について語られる際、このような表現が使われていたと考えられています。特に優秀な職人や商人が自分の働く場所を選べる一方で、店や組織は人手不足に悩まされる状況を表現するのに適した言葉だったのでしょう。自然界の観察から生まれた、人間社会の本質を突いた表現として定着していったと推測されます。
使用例
- 優秀なエンジニアは引く手あまただから、鳥は木を択べども木は鳥を択ばずで、会社側が条件を良くするしかない
- 人手不足の時代は完全に鳥は木を択べども木は鳥を択ばずの状況で、求職者が企業を選ぶ立場になっている
普遍的知恵
このことわざが語り継がれてきた背景には、人間社会における能力と選択の自由の関係という普遍的なテーマがあります。能力のある者は常により良い環境を求めて移動する自由を持ち、一方で組織や共同体は常に人材を必要とし続けるという構造は、時代が変わっても変わりません。
興味深いのは、このことわざが単なる不公平を嘆いているのではなく、むしろ現実を冷静に観察した結果として生まれている点です。優秀な人材が選択権を持つのは当然であり、それを受け入れる側は文句を言っても仕方がないという、ある種の達観が込められています。これは人材を確保したい側に対する戒めでもあります。選ばれる立場であることを自覚し、魅力的な環境を整える努力を怠ってはならないという教えなのです。
また、このことわざは能力主義の本質も突いています。能力のある者が優位に立つのは自然の摂理であり、それに対抗するには自らを魅力的な選択肢にするしかない。この厳しくも公平な現実認識こそが、先人たちが見抜いていた人間社会の真理なのでしょう。競争と選択の原理は、どの時代にも存在する人間活動の基本法則なのです。
AIが聞いたら
鳥が木を選ぶ瞬間だけを見れば、確かに鳥が有利に見える。でもゲーム理論で分析すると、実は木の側にも強力な戦略がある。それは「待つ」という戦略だ。
マッチング市場の研究では、選ばれる側が複数の選択者を同時に受け入れられる場合、長期的には選ばれる側が市場の主導権を握ることが分かっている。木は一羽の鳥だけでなく、何十羽もの鳥を同時に受け入れられる。つまり木は「ポートフォリオ戦略」を取れるのだ。一方、鳥は一本の木しか選べない。この非対称性が重要になる。
具体例で考えよう。就職市場では学生が企業を選ぶように見えるが、優良企業は毎年何千人もの応募者から選べる。一人の学生が入社を断っても、企業は次の候補者を選べばいい。でも学生は内定を断ると、次のチャンスが保証されない。この構造では、実は企業側が圧倒的に有利だ。
さらに興味深いのは、木が「選ばない」ことで間接的に選んでいる点だ。栄養を多く配分する枝、日当たりの良い場所など、木は資源配分によって「どの鳥により良い環境を提供するか」を決めている。これは受動的選択ではなく、能動的な市場設計なのだ。
現代人に教えること
このことわざは、現代を生きる私たちに二つの重要な視点を与えてくれます。まず、自分自身の能力を高めることの大切さです。選べる立場になるためには、自分を磨き続ける努力が必要です。スキルを身につけ、経験を積み、自分の価値を高めていくことで、人生の選択肢は確実に広がっていきます。あなたが今学んでいること、挑戦していることは、将来の自由につながっているのです。
同時に、組織やチームを率いる立場にある人、あるいは将来そうなる人には、選ばれる存在であり続ける努力の必要性を教えてくれます。優秀な人材に来てもらい、留まってもらうには、魅力的な環境を作らなければなりません。それは給与だけでなく、成長機会や働きやすさ、理念への共感など、多面的な魅力です。
このことわざの本質は、一方的な関係ではなく、相互の価値創造にあります。能力のある人が良い環境を選び、組織がその人を活かす場を提供する。この好循環を作ることこそが、個人にとっても組織にとっても幸せな関係なのです。
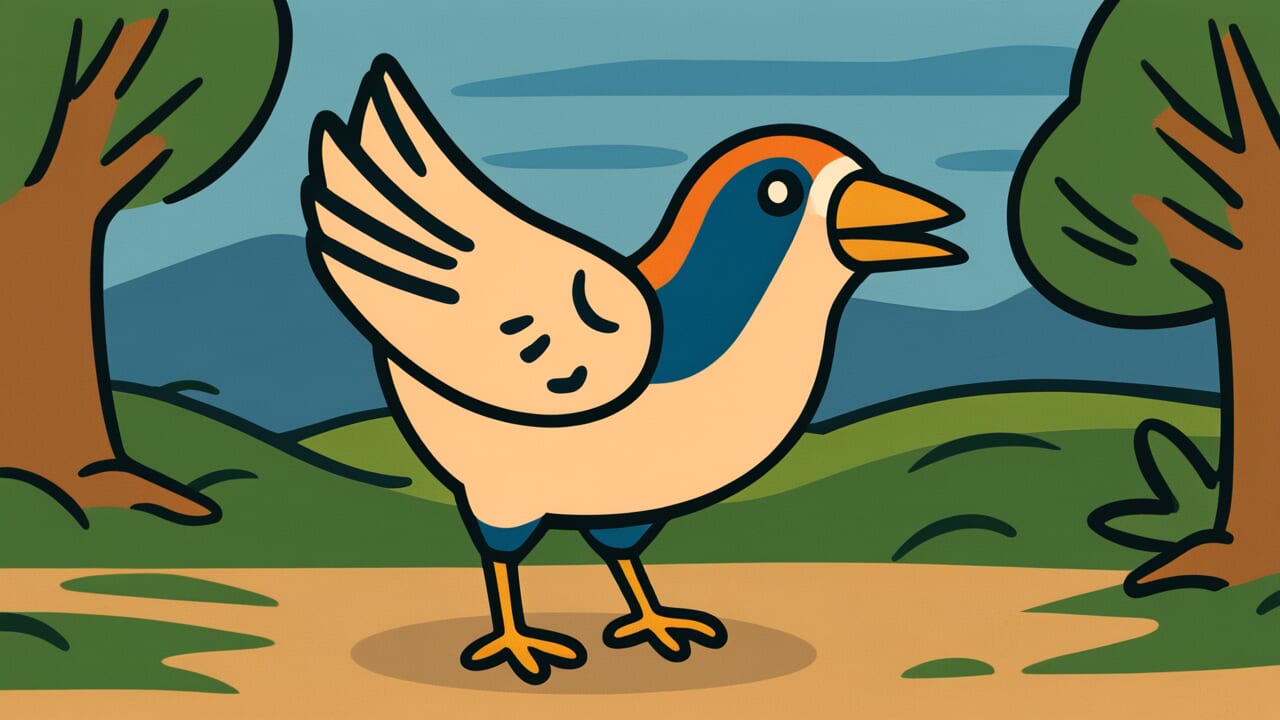


コメント