猪も七代目には豕になるの読み方
いのもしちだいめにはぶたになる
猪も七代目には豕になるの意味
このことわざは、野生の猪も代を重ねれば家畜の豚のように性質が変わってしまうという意味です。世代を経るうちに、本来持っていた特性や気質が失われ、まったく別のものに変化してしまうことを表しています。
特に、創業者の気概や武家の気風、家系の伝統など、初代が持っていた強さや誇りが、子孫の代になると失われていく様子を指して使われます。野生のイノシシは勇猛で力強い動物ですが、飼育された豚は穏やかで従順です。この対比が、人間の家系や組織における変化を見事に言い表しているのです。
現代では、創業家の企業精神が薄れていく様子や、名門の家柄が昔日の面影を失っていく状況などに使われます。環境や時代の影響を受けて、良くも悪くも元の姿から変わってしまうという、避けがたい変化の法則を示すことわざなのです。
由来・語源
このことわざの由来について、明確な文献上の記録は残されていないようですが、言葉の構成から興味深い考察ができます。
まず注目したいのは「猪」と「豕」という二つの漢字です。猪は野生のイノシシを指し、豕は家畜化された豚を意味します。実は生物学的には、豚はイノシシを家畜化したものであり、この二つは同じ種なのです。古代中国では、野生のイノシシを捕まえて飼育し、何世代もかけて家畜の豚へと変化させていきました。
「七代目」という具体的な数字が使われているのも興味深い点です。七という数字は、日本や中国の文化において「多い」「長い期間」を象徴的に表す数として用いられてきました。実際に七世代という意味ではなく、「長い年月を経て」という比喩的な表現と考えられています。
このことわざは、野生の猛々しいイノシシでさえ、飼育環境で何世代も過ごせば、おとなしい家畜の豚になってしまうという事実を踏まえています。環境が生物に与える影響の大きさ、そして世代を重ねることで起こる変化の不可逆性を、先人たちは鋭く観察していたのでしょう。人間社会においても、家系や組織が時代を経て変質していく様子を、この動物の変化に重ね合わせたと考えられています。
豆知識
イノシシと豚は生物学的には同じ種(Sus scrofa)に分類されます。DNA解析によれば、豚は約9000年前に東アジアや中東で独立してイノシシから家畜化されたことが分かっています。興味深いのは、家畜化された豚を野生に放すと、わずか数世代で再び牙が伸び、体毛が濃くなり、イノシシに近い姿に戻っていくという事実です。環境が生物の形質に与える影響の大きさを物語っています。
日本では「豕」という漢字は常用漢字ではないため、現代ではあまり見かけませんが、古典や漢文では頻繁に登場します。この漢字自体が、豚を囲いの中で飼育している様子を象形したものだと言われており、家畜化の歴史の古さを感じさせます。
使用例
- あの老舗企業も三代目になってすっかり保守的になった、猪も七代目には豕になるとはよく言ったものだ
- 創業者の開拓精神はどこへやら、猪も七代目には豕になるで、今の経営陣には冒険心のかけらもない
普遍的知恵
このことわざが教えてくれるのは、変化の不可避性という人間社会の深い真理です。どんなに強い意志や優れた資質も、環境と時間の前では形を変えていくという現実を、先人たちは見抜いていました。
なぜ人は変わってしまうのでしょうか。それは、生き残るために環境に適応する力が、私たちに備わっているからです。野生のイノシシが猛々しいのは、厳しい自然で生き延びるために必要だったから。しかし安全な囲いの中では、その気質は不要になります。人間も同じです。創業者が持っていた闘争心は、安定した組織の中では次第に必要とされなくなり、世代を経るごとに薄れていくのです。
このことわざには、変化を嘆く響きがありますが、同時に希望も含まれています。環境が性質を変えるなら、良い環境を作れば良い方向への変化も可能だということです。また、変化は避けられないからこそ、初心を意識的に保つ努力の大切さも教えてくれます。
人間は環境の産物であると同時に、環境を作る存在でもあります。この二重性を理解することが、このことわざが長く語り継がれてきた理由なのでしょう。変化を受け入れながらも、守るべきものは何かを問い続ける。その緊張感こそが、人間らしさなのかもしれません。
AIが聞いたら
野生のイノシシを飼育すると七代で家畜のブタになるという観察は、遺伝子本体は変わらないのに形質が変化する現象を捉えています。これは現代生物学でいうエピジェネティクスそのものです。
エピジェネティクスとは、DNA配列自体は変化しないまま、遺伝子のスイッチのオン・オフが変わる仕組みです。たとえば同じ遺伝子を持つ一卵性双生児でも、生活環境で体型や性格が変わるのはこのためです。興味深いのは、この遺伝子スイッチの状態が子孫に受け継がれることがあるという点です。ただし永遠には続きません。
線虫を使った実験では、ある環境変化による遺伝子発現の変化が子孫に伝わりますが、だいたい3世代から7世代でリセットされることが分かっています。つまり獲得形質は遺伝するけれど、数世代で消えるのです。「七代目」という数字は、まさにこの科学的な減衰期間と一致します。
江戸時代の人々は、飼育動物の観察から「変化は遺伝するが永久ではない」という生物学的真実を見抜いていたのでしょう。野生性が薄れていく過程を何世代も追跡した結果、七代あたりで完全に家畜化すると経験的に把握していた。これは分子レベルのメカニズムを知らずに、エピジェネティクスの時間スケールを正確に言い当てた驚くべき洞察です。
現代人に教えること
このことわざが現代人に教えてくれるのは、意識的な努力なしには本質は保てないという厳しくも大切な真実です。
私たちは日々、快適さや安定を求めて生きています。それ自体は悪いことではありません。しかし、安定した環境に身を置き続けると、知らず知らずのうちに挑戦する力や創造性が失われていくのです。これは個人にも、組織にも、家族にも当てはまります。
大切なのは、変化を恐れるのではなく、理解することです。環境が私たちを変えていくなら、自分がどんな環境に身を置くかを意識的に選ぶことができます。また、守りたい価値観や姿勢があるなら、それを次世代に伝える努力を怠ってはいけません。言葉で語り、行動で示し、環境を整える。そうした積極的な働きかけがなければ、大切なものは自然と失われていくのです。
同時に、変化を受け入れる柔軟性も必要です。すべてを昔のまま保つことが正しいわけではありません。時代に合わせて変えるべきものと、変えてはいけない核心を見極める知恵。それこそが、このことわざが私たちに求めている姿勢なのではないでしょうか。
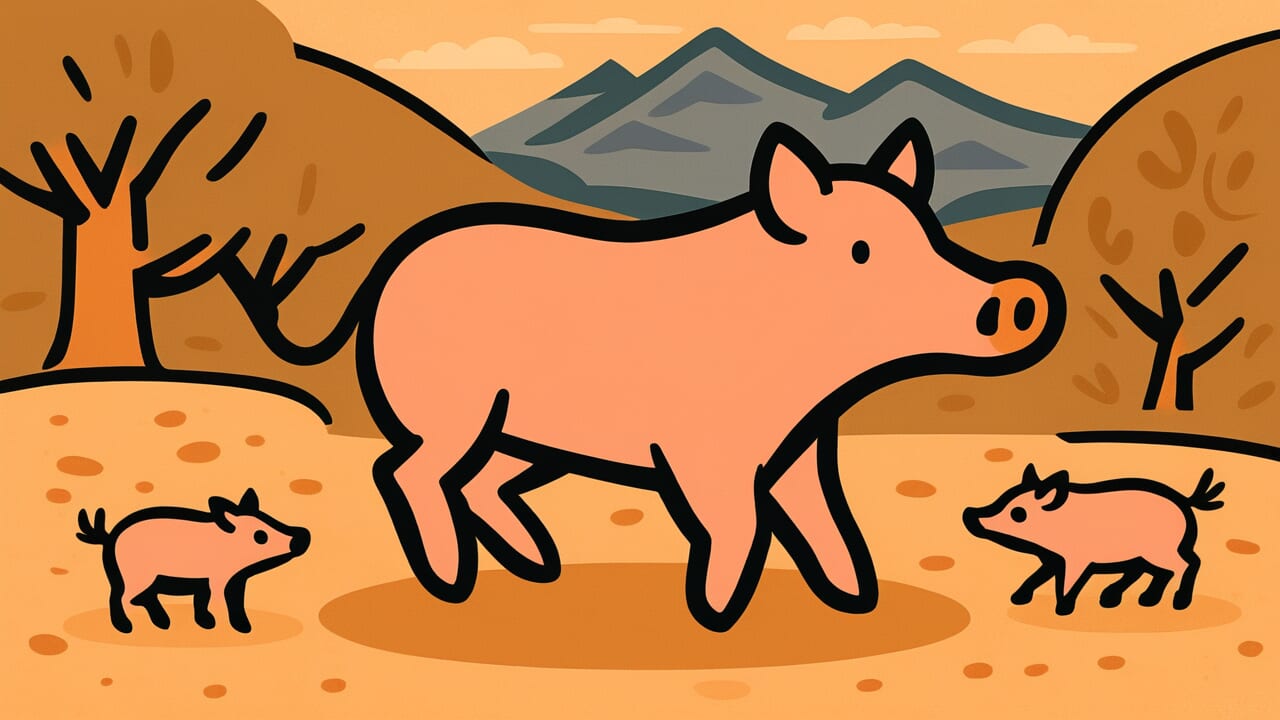


コメント