敢えて後れたるに非ず、馬進まざればなりの読み方
あえておくれたるにあらず、うますすまざればなり
敢えて後れたるに非ず、馬進まざればなりの意味
このことわざは、遅れているのは決して本人が怠けているからではなく、条件や環境が整っていないためだという意味を表しています。馬が進まなければ騎手がどんなに急いでも前に進めないように、人が目標を達成できないのは、必ずしもその人の努力不足や怠慢が原因ではないということです。
使う場面としては、誰かの遅れや未達成を責める前に、その背景にある客観的な事情を考慮すべきだと諭すときや、自分自身が思うように進めない状況を説明するときに用いられます。現代でも、プロジェクトの遅延や目標未達成の際、個人の能力や意欲だけでなく、リソース不足、システムの問題、外部環境など、本人の力ではどうにもならない要因があることを理解する必要性を示す言葉として通用します。表面的な結果だけで判断せず、真の原因を見極める公正さの大切さを教えてくれることわざです。
由来・語源
このことわざは、古典的な漢文調の表現で、日本の武家社会や儒教的な教養の中で育まれてきた言葉と考えられています。「敢えて」という言葉は「わざと」「故意に」という意味を持ち、「後れたる」は「遅れている」状態を指します。そして「非ず」で否定し、「馬進まざればなり」で真の理由を示すという、論理的な構造を持っています。
この表現の背景には、馬を用いた移動が一般的だった時代の実体験があると推測されます。当時、馬は重要な交通手段であり、目的地への到着が遅れる理由として、騎手の怠慢ではなく馬の状態や道路事情など、外的要因が大きく影響していました。馬が疲れていたり、病気であったり、あるいは道が悪かったりすれば、どんなに急いでも前に進めません。
この言葉は、単なる言い訳ではなく、物事の遅延には本人の意志や努力だけでは解決できない客観的な理由があることを、馬という具体的な例を通して示しています。武士道や儒教の影響を受けた日本社会では、責任の所在を明確にすることが重視されましたが、同時に公正な判断も求められました。このことわざは、表面的な結果だけで人を責めるのではなく、その背景にある真の原因を見極める知恵を伝えているのです。
使用例
- 新人の成績が伸びないのは、敢えて後れたるに非ず馬進まざればなりで、教育体制が整っていないからだ
- 彼のプロジェクトが遅れているのを責められないよ、敢えて後れたるに非ず馬進まざればなりで、予算が削られたんだから
普遍的知恵
このことわざが長く語り継がれてきた理由は、人間社会における根本的な問題、つまり「結果と原因の見極め」という永遠のテーマに触れているからです。人は目に見える結果に対して、すぐに誰かを責めたくなる性質を持っています。遅刻した人を見れば怠け者だと決めつけ、成果が出ない人を見れば能力不足だと判断してしまいがちです。
しかし、この短絡的な判断こそが、多くの誤解と不公正を生み出してきました。馬が進まなければ騎手は前に進めないという単純な事実は、私たちに深い洞察を与えてくれます。それは、人間の意志や努力だけでは動かせない現実が確実に存在するということです。
先人たちは、この真理を見抜いていました。どんなに優秀な人でも、道具が壊れていれば仕事はできません。どんなに誠実な人でも、情報が届いていなければ正しい判断はできません。人間の営みは、常に何かに依存し、何かに支えられています。個人の責任を問うことは大切ですが、その前に環境や条件を整える責任が社会全体にあるのです。
このことわざは、公正さとは何かを問いかけています。表面だけを見て人を裁くのではなく、その人が置かれた状況全体を理解しようとする姿勢こそが、真の公正さなのだと教えてくれるのです。
AIが聞いたら
制御システムには必ず「入力→処理→出力」という流れがあります。このことわざが面白いのは、人間が「処理部」で馬が「出力部」という分業構造を明確に示している点です。現代の制御理論では、システムの失敗を「センサー故障」「演算エラー」「アクチュエーター不良」の3つに分類しますが、このことわざは3番目のアクチュエーター不良、つまり実行部分の問題を指摘しています。
興味深いのは、制御工学における「可観測性」と「可制御性」の概念です。可観測性とは状態を観測できるか、可制御性とは制御できるかという性質ですが、このことわざの状況では馬の状態は観測できても制御できない状態、つまり可観測だが非可制御という最も厄介なケースを表しています。自動運転車で言えば、センサーは正常だがブレーキが故障している状態です。
さらに重要なのは、フィードバック制御の限界を示している点です。人間がどれだけ馬に指令を送っても、馬という実行系が応答しなければシステム全体が機能しません。これは現代のAI倫理で議論される「制御できないシステムの責任は誰が負うのか」という問題そのものです。制御理論的には、システム設計者は制御不能な要素を含むシステムを運用すべきではないのですが、現実には完全な制御など不可能です。このことわざは、その矛盾を2000年以上前に言語化していたのです。
現代人に教えること
現代社会でこのことわざが教えてくれるのは、人を評価する前に「その人が持っている道具は何か」を考える習慣の大切さです。あなたの職場で成果が出ていない同僚がいたら、まずその人が使っているシステムは古くないか、必要な情報は届いているか、サポート体制は整っているかを確認してみてください。
特にリーダーの立場にある人は、この視点が重要です。メンバーに結果を求める前に、結果を出せる環境を整える責任があります。最新のツールを提供する、適切な研修を行う、相談しやすい雰囲気を作る。これらは「馬を進ませる」ための条件なのです。
また、自分自身が思うように進めないときも、このことわざは救いになります。すべてを自分の責任だと抱え込まず、客観的に状況を分析してください。足りないリソースがあれば助けを求めることは、決して恥ずかしいことではありません。
このことわざは、結果だけを見る文化から、プロセスと環境を大切にする文化への転換を促しています。人を責める前に理解しようとする、その優しさと公正さこそが、より良い社会を作る第一歩なのです。
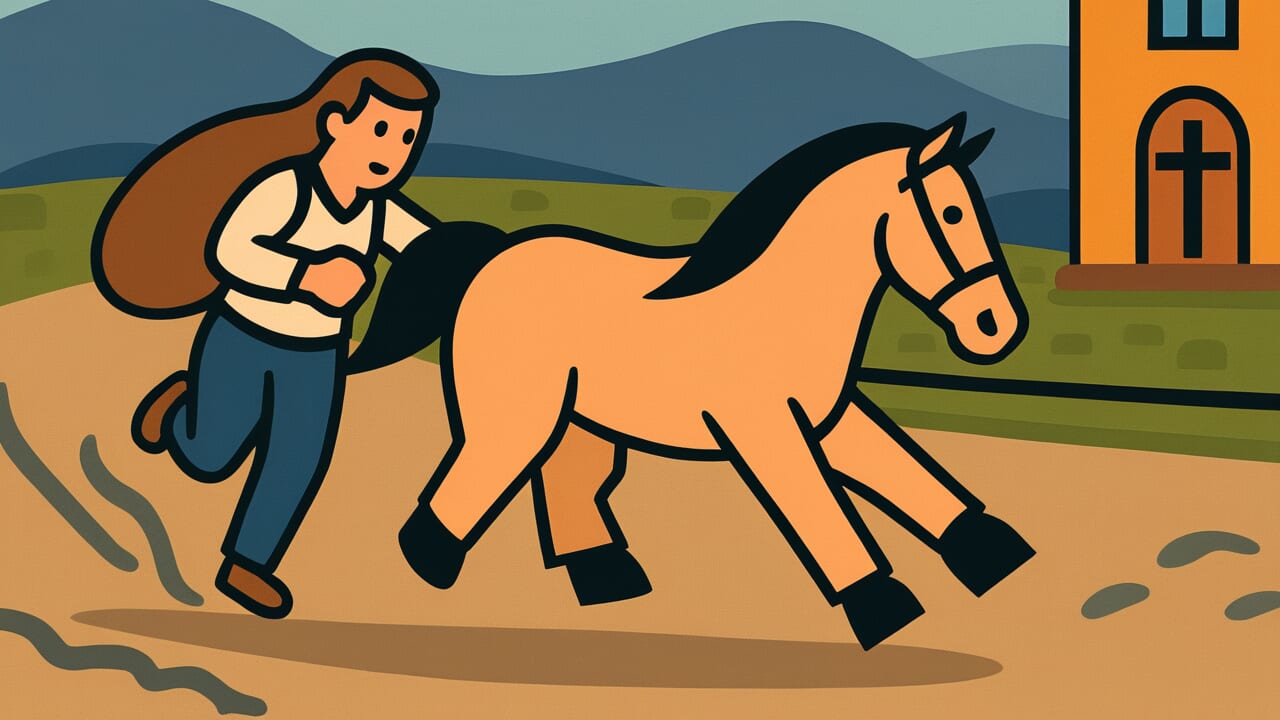


コメント