驢事未だ去らざるに馬事到来すの読み方
ろじいまださらざるにばじとうらいす
驢事未だ去らざるに馬事到来すの意味
このことわざは、一つの問題や困りごとがまだ解決していないうちに、新たな問題が次々と発生してしまう状況を表しています。
まさに現代でも誰もが経験する「泣きっ面に蜂」のような状況ですね。仕事でトラブルが発生して対応に追われているときに、さらに別の案件で問題が起きてしまう。家庭では子どもの病気の看病をしているときに、今度は自分が体調を崩してしまう。このように、問題が重なって起こる不運な状況を的確に表現したことわざなのです。
このことわざを使う理由は、単に「大変だ」と言うよりも、問題が連続して発生する特殊な状況を強調したいからです。一つずつなら何とか対処できるのに、重なってしまうからこそ困難になるという状況の特殊性を表現できるのですね。現代でも、この表現を知っている人が使えば、聞き手に「ああ、本当に大変な状況なんだな」と深く理解してもらえるでしょう。
由来・語源
このことわざの由来は、中国の古典に遡ると考えられています。「驢」はロバ、「馬」は馬を指し、どちらも荷物を運ぶ重要な家畜でした。古代中国では、これらの動物は商人や旅人にとって欠かせない存在だったのです。
「驢事」「馬事」という表現は、それぞれロバに関する問題、馬に関する問題を意味しています。一頭の動物に関するトラブルがまだ解決していないうちに、もう一頭の動物に関する新たな問題が発生するという状況を表現したものです。
このことわざが日本に伝わったのは、おそらく漢文の学習を通じてでしょう。江戸時代の文献にも見られることから、かなり古くから日本の知識人の間で使われていたと推測されます。
興味深いのは、日本では馬は身近な動物でしたが、ロバはそれほど一般的ではありませんでした。それでも「驢馬」という組み合わせが定着したのは、中国古典の権威と、この表現の持つリズムの良さが理由かもしれません。「驢事未だ去らざるに馬事到来す」という音の響きには、まさに次から次へと問題が押し寄せる様子が表現されているのですね。
使用例
- プロジェクトの締切に追われているのに、驢事未だ去らざるに馬事到来すで、今度は別の案件でも問題が発生してしまった
- せっかく風邪が治りかけたと思ったら、驢事未だ去らざるに馬事到来すで、今度は腰を痛めてしまった
現代的解釈
現代社会では、このことわざが表現する状況がより頻繁に、より複雑に発生するようになりました。情報化社会の特徴として、複数のタスクを同時並行で処理することが当たり前になり、一つの問題が解決する前に次の課題が舞い込むのは日常茶飯事です。
特にビジネスシーンでは、メールやチャット、電話など様々なチャンネルから絶え間なく新しい要求や問題が届きます。SNSの普及により、プライベートでも常に何かしらの対応を求められる状況が続いています。まさに「驢事未だ去らざるに馬事到来す」が現代人の日常を表現する言葉として、新たな意味を持つようになったのです。
しかし、現代では古典的な「不運」として諦めるのではなく、この状況をいかに効率的に管理するかが重要視されています。タスク管理ツールや優先順位付けの技術など、複数の問題を同時に扱うためのスキルが発達しました。
一方で、このことわざは現代人に重要な警鐘も鳴らしています。問題が次々と発生する状況に慣れすぎて、一つ一つの問題に丁寧に向き合うことを忘れがちになっているのではないでしょうか。古典の知恵は、時には立ち止まって根本的な解決を図ることの大切さも教えてくれているのです。
AIが聞いたら
現代のビジネス書は「マルチタスク能力」を成功の鍵として持て囃すが、スタンフォード大学の研究では、人間の脳は実際には同時処理ができず、タスク間を高速で切り替えているだけで、この切り替えコストによって作業効率が最大40%も低下することが判明している。
「驢事未だ去らざるに馬事到来す」は、まさにこの現象を数百年前から警告していた。ロバの仕事が終わらないうちに馬の仕事がやってくる状況は、現代人が陥りがちな「前のメールに返信しきれないうちに新しい会議が始まり、その準備も中途半端なまま次のプロジェクトが舞い込む」という悪循環そのものだ。
興味深いのは、東洋的時間観が「一つの事を完了させてから次へ移る」という直線的な処理を重視する点だ。これは禅の「一期一会」や茶道の「一つ一つの動作に集中する」思想と通底している。一方、西洋的な効率主義は「時間を節約するために複数のことを同時に」という発想に傾きがちだ。
実際、集中力研究の第一人者であるカル・ニューポート教授は、一つの作業に深く没入する「ディープワーク」こそが真の生産性を生むと結論づけている。古人が「驢事」と「馬事」を明確に分けて考えた知恵は、現代の脳科学が証明する理想的な作業スタイルを先取りしていたのである。
現代人に教えること
このことわざが現代人に教えてくれるのは、問題が重なることは人生の自然な一部だということです。完璧にコントロールしようとして疲れ果てるよりも、時には「そういうものだ」と受け入れる心の余裕を持つことが大切なのですね。
現代社会では、すべてを効率的に解決しなければならないというプレッシャーを感じがちです。しかし、このことわざは古くから人々が同じような状況に直面してきたことを教えてくれます。あなたが今直面している困難は、決して特別なものではないのです。
大切なのは、問題が重なったときこそ、優先順位を明確にすることです。すべてを同時に完璧に解決しようとせず、まずは最も重要なことから一つずつ取り組んでいけばよいのです。
そして、このような状況を経験することで、あなたはより強く、より柔軟になっていきます。問題が重なる経験は、実は人生の貴重な学びの機会でもあるのです。次に同じような状況に遭遇したとき、きっと今よりも上手に対処できるはずです。困難な時期こそ、自分の成長のチャンスだと捉えてみてくださいね。
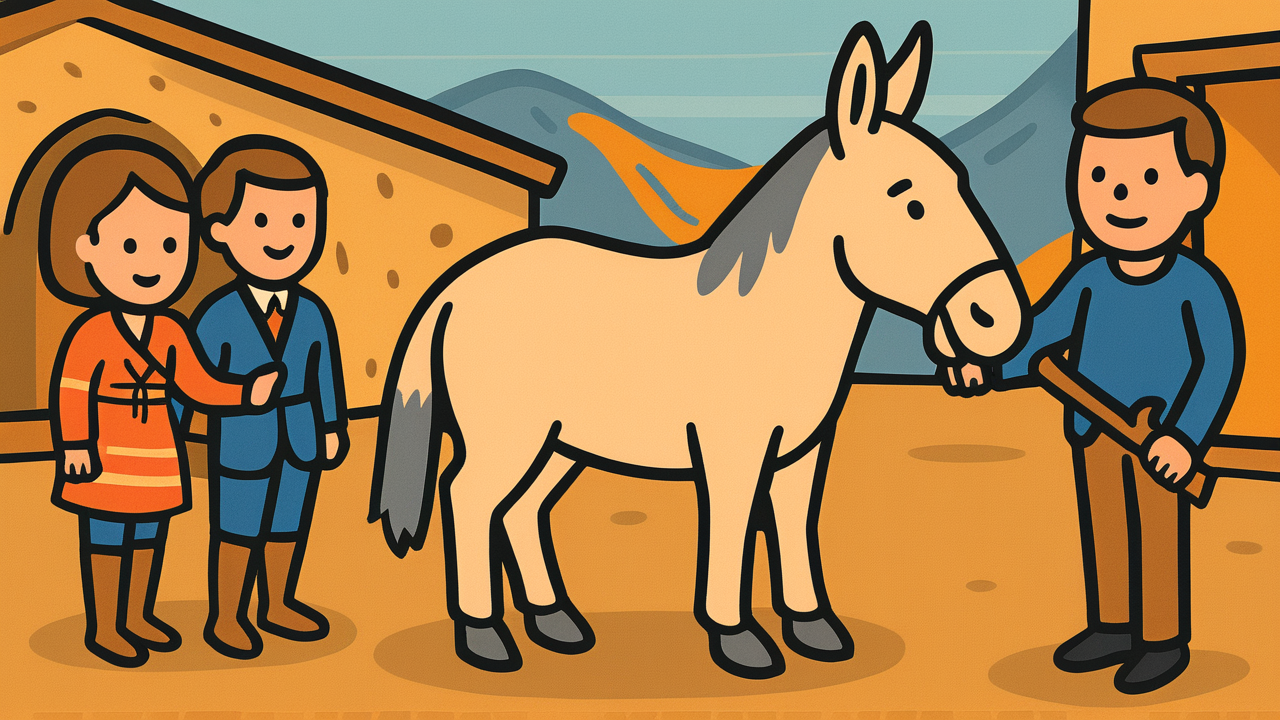
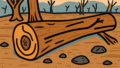

コメント