和を以て貴しとなすの読み方
わをもってとうとしとなす
和を以て貴しとなすの意味
このことわざは、人々が互いに協調し合うことを最も大切な価値とするという意味です。
ここでいう「和」とは、単に争いを避けることではなく、異なる意見や立場の人々が建設的な議論を通じて合意を形成し、共に歩んでいくことを指しています。「貴し」は尊いという意味で、調和を保つことが何よりも価値あることだと教えています。
このことわざが使われるのは、集団での意思決定や人間関係において対立が生じそうな場面です。個人の主張を押し通すのではなく、全体の調和を考慮しながら物事を進めることの重要性を説く際に用いられます。現代でも、チームワークを重視する場面や、多様な意見をまとめる必要がある状況で、この精神が活かされています。ただし、これは決して自分の意見を持たないことや、盲目的に従うことを意味するのではなく、建設的な対話を通じて最良の解決策を見つけることを重視する考え方なのです。
由来・語源
このことわざは、聖徳太子が制定したとされる十七条憲法の第一条に由来しています。「和を以て貴しと為し、忤ふること無きを宗とせよ」という文言が原典で、これが時代を経て現在の形に定着しました。
十七条憲法は推古天皇12年(604年)に制定されたとされる、日本最古の成文法の一つです。この第一条は、当時の政治的混乱を背景に、朝廷内の対立や豪族間の争いを収束させるための指針として示されました。聖徳太子は仏教思想と儒教思想を融合させ、調和を重視する統治理念を打ち出したのです。
興味深いのは、この「和」という概念が単なる仲良しを意味するのではなく、異なる意見や立場の人々が議論を重ねながらも、最終的には合意に達することを重視していた点です。原文の「忤ふること無きを宗とせよ」は、むやみに対立することなく、建設的な議論を通じて物事を決めていこうという意味が込められています。
この教えは日本の政治文化の根幹となり、後の時代にも受け継がれ、現代に至るまで日本人の価値観の基礎として定着しています。
豆知識
聖徳太子の十七条憲法で使われた「和」という字は、当時としては革新的な概念でした。中国の儒教では「礼」や「仁」が重視されていましたが、聖徳太子はあえて「和」を第一条に据えることで、日本独自の価値観を示そうとしたと考えられています。
この「和を以て貴しとなす」は、実は完全な文ではなく、本来は「和を以て貴しと為し、忤ふること無きを宗とせよ」という長い文の前半部分です。後半の「忤ふること無きを宗とせよ(むやみに逆らうことを避けよ)」という部分が省略されて広まったため、本来の意味とは少し異なる解釈が生まれることもあります。
使用例
- プロジェクトで意見が分かれているけれど、和を以て貴しとなすの精神で、みんなで話し合って最良の案を見つけよう
- 部署間の対立が続いているが、和を以て貴しとなすという言葉を思い出し、建設的な議論の場を設けることにした
現代的解釈
現代社会において、この古いことわざは新たな意味を持ち始めています。グローバル化が進む中で、異なる文化や価値観を持つ人々と協働する機会が増え、「和」の概念はより複雑で重要なものとなっています。
特にリモートワークやオンライン会議が普及した現在、物理的な距離を超えて調和を築くことが求められています。デジタルコミュニケーションでは、対面での微細な感情の読み取りが困難になるため、より意識的に「和」を作り出す努力が必要になっているのです。
一方で、現代では個人の多様性や創造性を重視する価値観も強まっており、従来の「和」の解釈に疑問を持つ声もあります。画一的な調和よりも、多様な意見や個性を活かしながらも共通の目標に向かう「新しい和」が模索されています。
SNSやオンラインコミュニティでは、異なる意見が激しく対立することも多く、建設的な議論よりも感情的な対立が目立つ場面が増えています。こうした状況だからこそ、本来の「和を以て貴しとなす」の精神、つまり異なる立場の人々が敬意を持って対話し、合意を形成していく姿勢が、改めて注目されているのです。現代の「和」は、違いを認め合いながらも共に前進する、より成熟した調和のあり方を示しているといえるでしょう。
AIが聞いたら
聖徳太子が「和を以て貴しとなす」で表現した「和」は、実は現代の私たちが思っているものと正反対だった。
十七条憲法の原文を見ると「咸く諧ひて論ふ」という表現がある。これは「みんなで活発に議論せよ」という意味だ。つまり、異なる意見を持つ人々が遠慮なく発言し、徹底的に話し合うことこそが「和」だったのである。
ところが現代日本では、この言葉が「みんな仲良く、波風を立てるな」という同調圧力の根拠として使われている。会議で反対意見を言うと「和を乱す人」とレッテルを貼られる。これは聖徳太子の意図と真逆だ。
興味深いのは、この誤解が生まれた背景にある。江戸時代の身分制度や戦時中の統制社会を通じて、「和」は「上に従うこと」へと意味が変化していった。本来は「対等な立場での建設的な議論」を指していたのに、いつの間にか「権力者に逆らわない従順さ」にすり替わってしまった。
現代の日本企業で「忖度」や「空気を読む」文化が根強いのも、この歴史的な意味の変化と無関係ではない。聖徳太子が現代の会議室を見たら、「これは和ではない」と驚くかもしれない。真の「和」を取り戻すには、むしろ積極的に異論を歓迎する姿勢が必要なのだ。
現代人に教えること
このことわざが現代の私たちに教えてくれるのは、真の強さとは自分の意見を押し通すことではなく、異なる価値観の人々と共に最良の答えを見つけ出す力だということです。
現代社会では、SNSで簡単に同じ意見の人とつながれる一方で、異なる考えの人との対話が減っています。しかし、本当に価値ある解決策は、多様な視点が交わる場所でこそ生まれるものです。あなたの職場でも、家庭でも、地域でも、「和を以て貴しとなす」の精神を実践してみてください。
それは相手の意見に盲目的に従うことではありません。自分の考えをしっかり持ちながらも、相手の立場を理解しようとする姿勢です。建設的な議論を重ね、時には妥協し、時には新しいアイデアを生み出していく。そんな関係性こそが、現代に必要な「和」なのです。
一人ひとりが異なる個性を持ちながらも、共通の目標に向かって歩んでいく。そんな調和を築くことができれば、あなたの周りはきっとより豊かで創造的な場所になるはずです。
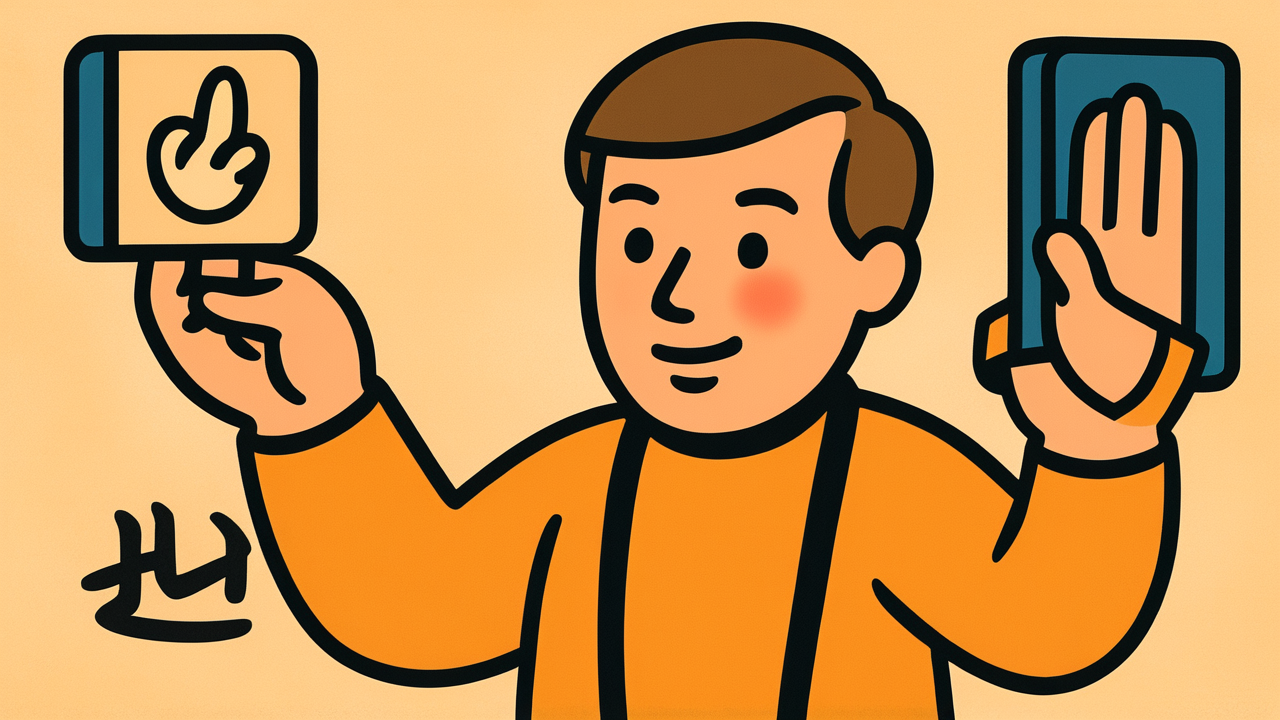


コメント