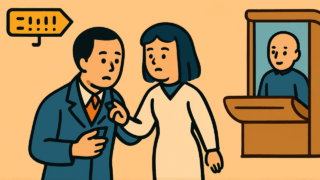 ことわざ
ことわざ 下衆の後知恵の意味・由来・使い方|日本のことわざ解説
下衆の後知恵の読み方げすのあとぢえ下衆の後知恵の意味「下衆の後知恵」とは、その場では何も言えなかった人が、物事が終わった後になってから「ああすればよかった」「こうすべきだった」と偉そうに批評することを指します。このことわざは、事前には建設的...
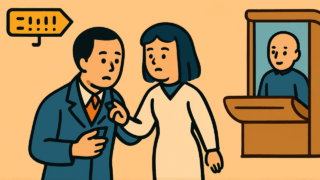 ことわざ
ことわざ 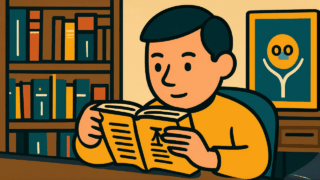 ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ 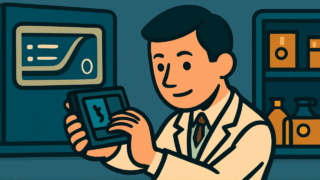 ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ 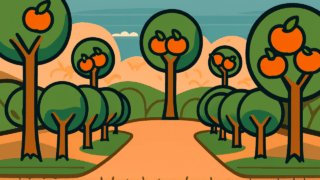 ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ 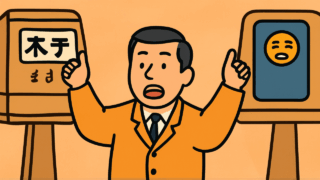 ことわざ
ことわざ  ことわざ
ことわざ